天井裏のハクビシンを追い出すには?【光と音で撃退】安全で効果的な3つの追い出し方法を解説

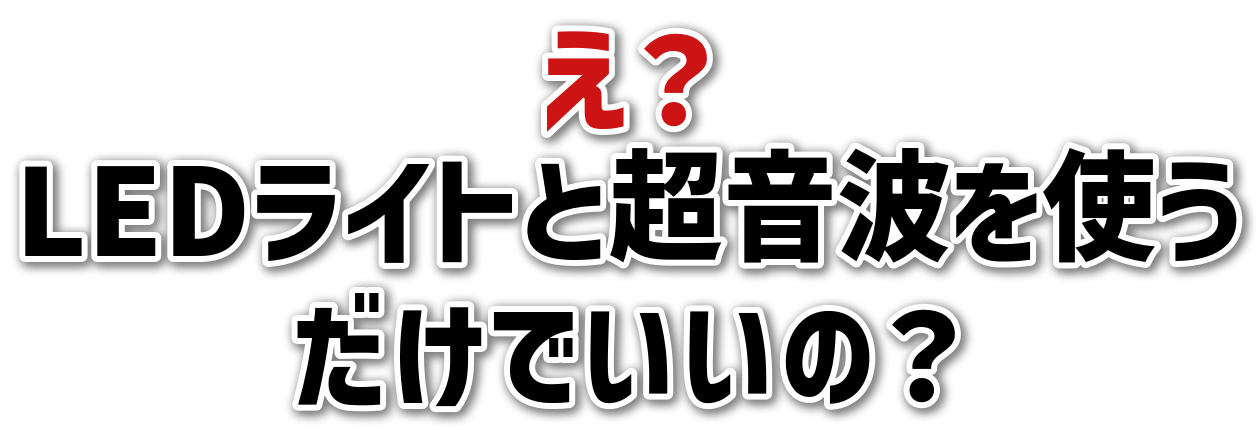
【この記事に書かれてあること】
真夜中、天井裏から「ガサガサ」という音が…。- 天井裏の異音や足音はハクビシン侵入のサイン
- 光と音を組み合わせた効果的な追い出し方法
- 強力LEDライトと超音波発生器の使い分け
- 屋根や外壁の隙間封鎖で再侵入を防止
- センサーライト設置や餌場撲滅で長期的な対策
これはハクビシンの侵入サインかもしれません。
でも大丈夫、光と音を味方につければ、ハクビシンを追い出せます!
本記事では、強力LEDライトや超音波発生器の効果的な使用法から、ラジオや金属音の活用術まで、具体的な対策をご紹介。
さらに、隙間封鎖や餌場撲滅など、再侵入を防ぐ5つの方法もお教えします。
ハクビシン撃退で、安心して眠れる夜を取り戻しましょう!
【もくじ】
天井裏のハクビシン被害!その実態と対策

天井裏からの「異音」に要注意!ハクビシンの侵入サイン
天井裏から聞こえる異音は、ハクビシン侵入の重要なサインです。すぐに対策を取りましょう。
夜中に「ガサガサ」「トコトコ」という音が天井裏から聞こえてきたら要注意です。
これはハクビシンが侵入している可能性が高いサインなんです。
ハクビシンは夜行性の動物で、日中は静かにしていますが、夜になると活発に動き回ります。
「え?でも、ネズミかもしれないんじゃ…」と思うかもしれません。
でも、ハクビシンの足音はネズミよりもずっと大きいんです。
体重が3〜5kgもあるので、その重さで天井裏を歩く音は結構はっきりと聞こえます。
他にも、こんな音に注意が必要です。
- 「ガリガリ」という噛む音(電線や木材を噛んでいる可能性大)
- 「キュッキュッ」という鳴き声(特に春と秋の繁殖期)
- 「ドタッ」という落下音(天井裏で転げ回っている)
「まあ、そのうち出て行くだろう」なんて放っておくと、大変なことになっちゃうかもしれません。
早めの対応が鍵なんです。
音がしたら、まずは侵入経路を探してみましょう。
侵入経路を特定!「屋根裏」が最多の侵入口
ハクビシンの最も多い侵入経路は屋根裏です。わずか6cmの隙間があれば侵入できてしまいます。
ハクビシンは驚くほど器用な動物なんです。
その体の大きさからは想像できないほど、小さな隙間から侵入してきます。
「えっ、そんな狭いところから入れるの?」と思うかもしれませんが、なんとわずか6cmの隙間があれば、体をくねらせて入り込んでしまうんです。
侵入経路で最も多いのが屋根裏です。
具体的には以下のような場所がよく狙われます。
- 屋根と壁の接合部の隙間
- 破損した瓦の下
- 換気口や通気口
- 軒下の隙間
- 屋根裏への点検口
木や雨樋を使って屋根まで簡単に登ってしまうんです。
「うちは2階建てだから大丈夫」なんて油断は禁物です。
侵入経路を特定するコツは、家の外回りをよく観察することです。
特に夕方や夜明け前に、ハクビシンが活動を始める時間帯に注意深く見てみましょう。
足跡や爪痕、糞の跡などが見つかれば、そこが侵入経路の可能性が高いです。
「でも、どこから入ってきているかわからない…」という場合は、専門家に相談するのも一つの手段です。
経験豊富な目で、見落としがちな侵入口を見つけてくれるかもしれません。
糞尿被害や断熱材破壊!放置すると「大惨事」に
ハクビシンの天井裏侵入を放置すると、糞尿被害や断熱材の破壊など深刻な問題に発展します。早急な対策が必要です。
「まあ、しばらく様子を見よう」なんて考えていると、とんでもないことになりかねません。
ハクビシンが天井裏に住み着くと、次々と問題が発生するんです。
まず最も深刻なのが、糞尿による被害です。
ハクビシンは決まった場所で排泄する習性があるので、天井裏の一箇所に糞尿が溜まっていきます。
そうすると…
- 天井にシミができる
- 家中に悪臭が漂う
- 衛生面で非常に危険(病気の原因に)
ハクビシンは巣作りのために断熱材を噛み砕いてしまいます。
「ガリガリ」という音が聞こえたら、もう手遅れかもしれません。
断熱効果が落ちて、冬は寒く夏は暑い家になってしまうんです。
さらに恐ろしいのが、電線への被害です。
ハクビシンは電線を噛む習性があります。
「チクチク」という音が聞こえたら要注意。
最悪の場合、漏電や火災の原因になることも。
「え?そんなに深刻なの?」と思われるかもしれません。
でも、これらの被害は時間とともにどんどん大きくなっていきます。
早めに対策を取らないと、修理費用がかさんでしまうんです。
だからこそ、ハクビシンの侵入に気づいたら、すぐに行動を起こすことが大切です。
「明日から対策しよう」ではなく、今すぐ始めましょう。
光と音を活用した追い出し方法!効果的な「撃退策」
光と音を組み合わせた方法が、ハクビシンを追い出す効果的な撃退策です。LEDライトと超音波発生器を活用しましょう。
ハクビシンは光と音に敏感な生き物なんです。
この特性を利用して、天井裏から追い出す作戦を立てましょう。
「でも、どうやって?」と思われるかもしれません。
具体的な方法をご紹介します。
まず、光による撃退です。
ハクビシンは暗い場所を好むので、明るい光は大の苦手。
天井裏に強力なLEDライトを設置しましょう。
ポイントは、
- できるだけ広範囲を照らす
- 点滅させると効果アップ
- 赤色光が特に効果的
ハクビシンの嫌いな音を利用します。
おすすめは超音波発生器です。
人間には聞こえませんが、ハクビシンにとっては不快な音なんです。
他にも、
- ラジオの人の声
- 金属音(鍋や皿を叩く音)
- 犬の鳴き声(録音したもの)
「光と音、どっちがいいの?」と迷うかもしれません。
実は、両方を組み合わせるのが最も効果的なんです。
光で不快にさせつつ、音でさらにストレスを与えるわけです。
ただし、注意点があります。
ハクビシンを追い詰めすぎると、攻撃的になる可能性があります。
「ゆっくり」「じわじわ」と追い出すのがコツです。
また、出口をしっかり確保することも忘れずに。
この方法を数日間続けると、多くの場合ハクビシンは自ら出ていきます。
「やった!出て行った!」と喜ぶのはまだ早いですよ。
次は再侵入を防ぐ対策が重要になってきます。
やってはいけない!「毒餌」は違法で逆効果
ハクビシン対策で絶対にやってはいけないのが毒餌の使用です。違法なだけでなく、逆効果になる可能性もあります。
「早く追い出したい!」という気持ちはよくわかります。
でも、毒餌の使用は絶対にダメです。
なぜなら…
- 法律で禁止されている(罰則の対象に)
- 他の動物にも危険(生態系を乱す)
- 死骸の処理が大変(腐敗臭の問題も)
それも間違いです。
ハクビシンはネズミと違い、殺鼠剤への耐性が強いんです。
効果がないどころか、かえって餌付けになってしまう可能性があります。
さらに恐ろしいのは、毒餌を食べたハクビシンが家の中で死んでしまうこと。
そうなると…
- 死骸を見つけるのが困難
- 腐敗臭が家中に充満
- ウジ虫の発生
「うわっ、最悪…」ですよね。
では、どうすればいいのでしょうか?
前述の光と音を使った方法や、専門家による捕獲など、人道的な方法を選びましょう。
少し時間はかかるかもしれませんが、安全で確実な方法なんです。
そして忘れてはいけないのが、侵入経路をふさぐことです。
ハクビシンを追い出しても、また入ってこられては元の木阿弥です。
家の周りをよく点検して、小さな隙間も見逃さないようにしましょう。
「急がば回れ」ということわざがありますが、ハクビシン対策にもピッタリ当てはまります。
焦らず、適切な方法で対処することが、長期的に見て最も効果的なんです。
光と音でハクビシンを追い出す!具体的な対策法
強力LEDライトvs超音波発生器!どちらが効果的?
強力LEDライトと超音波発生器、どちらもハクビシン対策に有効ですが、組み合わせて使うのが最も効果的です。「どっちを買えばいいの?」って迷っちゃいますよね。
実は、両方とも効果があるんです。
でも、ハクビシンの個性によって効き目が違うこともあるんです。
まずは強力LEDライトについて。
ハクビシンは夜行性なので、突然の明るさに弱いんです。
「うわっ、まぶしい!」って感じでしょうか。
特に赤色のLEDライトが効果的です。
なぜかというと、ハクビシンには赤色が特に刺激的に見えるからなんです。
一方、超音波発生器も強い味方です。
人間には聞こえない高い周波数の音を出すんですが、ハクビシンにはこれがものすごく不快なんです。
「キーーーン」という感じでしょうか。
耳をつんざくような音なので、いたたまれなくなるわけです。
でも、どっちがより効果的かというと…実は個体差があるんです。
- 光に敏感なハクビシン
- 音に敏感なハクビシン
- どちらにも強いハクビシン
だから、両方を組み合わせて使うのが一番確実なんです。
使い方のコツは、不規則に点滅させたり、音の強さを変えたりすること。
「いつも同じじゃつまらない」なんて、ハクビシンも慣れっこになっちゃうんです。
ちなみに、これらの機器を使う時は近所迷惑にならないよう注意してくださいね。
「隣の家からピカピカ光って眠れない!」なんて苦情が来たら大変です。
ラジオの深夜放送vs金属音!ハクビシンの嫌いな音とは
ハクビシンは人の声や金属音が苦手です。ラジオの深夜放送や鍋を叩く音を活用しましょう。
「え?ラジオで追い出せるの?」って思いましたか?
実はこれ、意外と効果的なんです。
ハクビシンは人間の声にとっても警戒心を抱くんです。
特に深夜放送がおすすめ。
なぜかというと…
- 夜中はハクビシンが活動する時間
- 深夜放送は声のトーンが落ち着いている
- 長時間連続で流せる
でも、ラジオだけじゃないんです。
金属音もハクビシンには「ギャー!」ってくらい苦手なんです。
例えば…
- 鍋やフライパンを叩く音
- 金属製のスプーンで鍋の底をコツコツ叩く音
- アルミホイルをクシャクシャする音
「カンカン」「ガチャガチャ」という不規則な音に、ハクビシンはびっくりしちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
あまりにも大きな音を出し続けると、近所迷惑になっちゃいます。
「隣の家から変な音がする…」なんて思われたら困りますよね。
だから、音量調整は慎重に行いましょう。
また、ハクビシンも慣れっこになる可能性があります。
「またか〜」って感じで無視されちゃうかもしれません。
だから、音の種類や流すタイミングを変えるのがコツです。
例えば、こんな感じで組み合わせてみるのはどうでしょうか?
- 深夜0時〜2時:ラジオの深夜放送
- 2時〜3時:金属音
- 3時〜4時:再びラジオ
光と音の「組み合わせ」が鍵!相乗効果で撃退
光と音を組み合わせることで、ハクビシン撃退の効果が劇的にアップします。相乗効果を狙いましょう。
「光だけじゃダメ?音だけじゃいけないの?」って思うかもしれません。
でも、実は両方一緒に使うのがハクビシン撃退の極意なんです。
なぜかというと、ハクビシンの五感を同時に刺激できるからです。
例えるなら、暗い部屋でくつろいでいるときに、突然まぶしい光が目に入って、同時に大きな音が耳に飛び込んでくるような感じ。
びっくりしちゃいますよね。
具体的には、こんな組み合わせが効果的です。
- 強力LEDライト + 超音波発生器
- 点滅するライト + ラジオの深夜放送
- センサーライト + 金属音の録音
でも、ただ同時に使えばいいってわけじゃありません。
ここで大切なのがタイミングです。
例えば…
- まず、静かに明かりをつける
- 30秒後、音を流し始める
- 1分後、明かりを点滅させる
- 2分後、音量を上げる
「何かおかしいぞ…」「やばい、逃げなきゃ!」ってハクビシンの気持ちが高まっていくイメージですね。
ただし、注意点もあります。
あまりに過激な方法だと、ハクビシンが逆上して暴れる可能性もあるんです。
「ギャー!どうしよう!」って感じで、家の中を荒らし回っちゃうかもしれません。
だから、徐々に強めていって、ハクビシンが自分から出ていくのを待つのがコツです。
「ゆっくりだけど確実に」が合言葉ですね。
そして、光と音の組み合わせを使う時は、必ず出口を確保しておきましょう。
「逃げたいけど逃げ場がない!」なんて状況は避けたいですからね。
天井裏の「光源配置」のコツ!死角をなくす工夫
天井裏の光源配置は、死角をなくすことが重要です。複数の光源を効果的に配置して、ハクビシンの逃げ場をなくしましょう。
「光を当てればいいんでしょ?」って思うかもしれません。
でも、実はそれだけじゃ不十分なんです。
ハクビシンは賢くて、暗い場所を見つけるとそこに隠れちゃうんです。
だから、死角をなくすことが大切。
どうすればいいのかというと…
- 複数の光源を使う
- 天井裏の形状に合わせて配置する
- 反射板を活用する
まず、複数の光源を使うことから始めましょう。
天井裏の広さにもよりますが、最低でも3〜4個は必要です。
「え?そんなにいるの?」って思うかもしれませんが、これが効果的なんです。
次に、配置のコツ。
天井裏の形状をよく観察して、光が届きにくい場所を把握しましょう。
例えば、梁の影になる部分や、屋根の傾斜で暗くなる場所など。
そういった場所に重点的に光を当てるんです。
具体的な配置例を挙げてみましょう。
- 天井裏の中央に1つ
- 四隅にそれぞれ1つずつ
- 特に暗くなりやすい場所に追加で1〜2個
さらに、反射板の活用も効果的です。
アルミホイルや鏡を使って、光を反射させるんです。
これで、直接光が当たりにくい場所も明るくできます。
「へえ、そんな方法があるんだ!」って感じですよね。
ただし、注意点もあります。
強すぎる光はハクビシンを過度に興奮させてしまう可能性があります。
「わー!まぶしすぎる!」って暴れだすかもしれません。
だから、光の強さは調整可能なタイプを選ぶのがおすすめです。
また、電気代のこともお忘れなく。
「えっ、電気代バカ高くなっちゃった!」なんてことにならないよう、こまめにオンオフできる仕組みを作りましょう。
例えば、人感センサーと連動させるのも良いアイデアです。
音源の「設置場所」と「音量調整」で効果アップ!
音源の設置場所と音量調整を工夫することで、ハクビシン撃退の効果が大幅にアップします。効果的な配置と適切な音量設定がポイントです。
「音を出せばいいんでしょ?」なんて簡単に考えていませんか?
実は、音源の設置場所と音量調整がとっても大切なんです。
まず、設置場所のコツをご紹介します。
- ハクビシンの侵入経路付近に置く
- 天井裏の中央よりも端に寄せる
- 複数の音源を分散配置する
それは、ハクビシンを効果的に追い出すためなんです。
例えば、侵入経路付近に置くのは、ハクビシンが家に入ってくる瞬間から「ヤバイ!」と思わせるため。
「入った途端に嫌な音かよ…」ってハクビシンも引き返したくなっちゃうんです。
端に寄せるのは、中央だと音が拡散しちゃうから。
端に置くことで、音の反射を利用して天井裏全体に行き渡らせるんです。
「おっ、賢いな!」って思いました?
そして、複数の音源を使うのがベストです。
例えば…
- 侵入口付近に1つ
- 天井裏の奥に1つ
- ハクビシンがよく現れる場所に1つ
次に、音量調整のポイントです。
これが意外と難しいんです。
大きすぎても小さすぎてもダメ。
「じゃあ、どうすればいいの?」って思いますよね。
ポイントは、段階的に音量を上げていくこと。
例えば…
- 最初の3日間は小さめの音量
- 次の3日間は中くらいの音量
- それでも効果がない場合は大きな音量
「少しずつ嫌になってきた…」ってハクビシンの気持ちが高まっていくイメージですね。
ただし、注意点も。
あまりに大きな音を出し続けると、近所迷惑になっちゃいます。
「隣の家からうるさい音がする…」なんて苦情が来たら大変です。
だから、音量調整は慎重に行いましょう。
最後に、音の種類を変えるのも効果的です。
「いつも同じ音じゃつまらない」なんて、ハクビシンも慣れちゃうかもしれません。
だから、例えばラジオと金属音を交互に使うとか、工夫が必要です。
こういった音源の設置と調整、ちょっと面倒くさいって思いましたか?
でも、効果は抜群なんです。
「やった!やっとハクビシンがいなくなった!」って喜べる日も近いはず。
頑張って試してみてくださいね。
ハクビシン撃退後の再侵入防止策!長期的な解決法

屋根や外壁の「隙間封鎖」が最重要!6cm以下に注意
屋根や外壁の隙間封鎖は、ハクビシンの再侵入を防ぐ最も重要な対策です。6cm以下の隙間も見逃さず封鎖しましょう。
「えっ、6cmの隙間からハクビシンが入れるの?」って驚きませんか?
実は、ハクビシンは驚くほど体をくねらせて小さな隙間から侵入できるんです。
だから、6cm以下の隙間も油断大敵。
見つけたら必ず封鎖しましょう。
では、どんな場所を重点的にチェックすればいいのでしょうか?
- 屋根と壁の接合部
- 換気口や排気口の周り
- 軒下や破損した外壁
- 瓦のずれや隙間
- 雨樋の取り付け部分
「えっと、何を使って封鎖すればいいの?」って思いましたよね。
おすすめの材料をご紹介します。
- 金属製のメッシュ:丈夫で噛み切られにくい
- コンクリートやモルタル:隙間を完全に埋められる
- 発泡ウレタン:細かい隙間も埋められる
- ステンレス製の板:平らな面の補強に最適
「よーし、全部塞いじゃえ!」なんて思わないでくださいね。
家の換気は大切です。
必要な換気口は金属製の網で覆うなど、工夫が必要です。
それから、高所作業になることが多いので安全には十分気をつけましょう。
「ちょっとぐらい…」は禁物です。
はしごの固定や安全帯の使用を忘れずに。
こうして隙間を封鎖すれば、ハクビシンの侵入をグッと防げます。
「ふう、これで安心」なんて油断は禁物。
定期的な点検も忘れずにね。
センサーライトの設置で「夜間の警戒」を強化!
センサーライトの設置は、夜間のハクビシン対策として非常に効果的です。突然の明るさにハクビシンは驚いて逃げ出します。
「夜中にハクビシンが来るんでしょ?どうやって追い払うの?」って思いませんか?
そこで活躍するのがセンサーライトなんです。
ハクビシンは夜行性。
暗闇が大好きなんです。
そこに突然、明るい光が!
「うわっ、まぶしい!」ってハクビシンは驚いて逃げ出すわけです。
では、センサーライトをどう設置すればいいのでしょうか?
ポイントを押さえましょう。
- 侵入しそうな場所を重点的に照らす
- 複数のライトで死角をなくす
- 光の向きは下向きに(近所迷惑防止)
- センサーの感度調整を忘れずに
大丈夫、最近のセンサーライトは省エネ設計。
それに、ハクビシンが来ない時は点灯しないので、思ったほど電気代はかかりません。
ただし、注意点もあります。
人の往来が多い場所だと、頻繁に点灯して逆効果になることも。
「あれ?またついた」なんてことになると、ハクビシンが慣れちゃうかもしれません。
そこで、ちょっとしたコツをご紹介。
- 赤色LEDを使う(ハクビシンには特に刺激的)
- 点滅するタイプを選ぶ(より効果的)
- 音声警報付きのものを使う(光と音のダブル効果)
「へえ、そんな方法があるんだ!」って思いましたよね。
センサーライトの設置、ちょっと面倒くさいかもしれません。
でも、一度設置すれば長期的な対策になります。
「よし、やってみよう!」って気持ちになりましたか?
頑張ってトライしてみてくださいね。
果樹の剪定と「餌場撲滅」で誘引要因を排除
果樹の剪定と餌場の撲滅は、ハクビシンを寄せ付けない環境作りの重要なポイントです。誘引要因を排除して、根本的な解決を目指しましょう。
「どうして家の周りにハクビシンが来るの?」って不思議に思いませんか?
実は、餌を求めてやって来ているんです。
特に果樹や野菜が大好物。
「うちの庭、ハクビシンにとっては天国みたいなもの?」なんて冗談じゃすみません。
では、どうすれば餌場を撲滅できるでしょうか?
ポイントをまとめてみました。
- 果樹の枝を剪定し、実を取りやすくする
- 熟した果実はすぐに収穫する
- 落下した果実は放置しない
- 生ゴミの管理を徹底する
- コンポストは密閉型を使用する
枝を低く、まばらにすることで、ハクビシンが登りにくくなります。
「えっ、木を切るの?」って心配かもしれません。
でも、適切な剪定は木の健康にも良いんです。
一石二鳥ですね。
ただし、注意点もあります。
急激な環境変化は逆効果。
「よーし、一気にやっつけるぞ!」なんて意気込むのはNG。
徐々に改善していきましょう。
具体的な手順を見てみましょう。
- まず、落下果実を毎日拾う習慣をつける
- 次に、低い位置の枝から少しずつ剪定を始める
- コンポストを密閉型に変更する
- 最後に、庭全体の見通しを良くする
「ふむふむ、こうすれば良いのか」って納得できましたか?
餌場の撲滅、ちょっと大変そうに感じるかもしれません。
でも、これこそがハクビシン対策の根本なんです。
「よし、頑張ってみよう!」その意気込みが大切です。
一緒に頑張りましょう!
「忌避剤」の効果的な使用法!天然素材も活用
忌避剤の効果的な使用は、ハクビシン対策の強力な味方です。市販の製品だけでなく、天然素材を活用することで、より安全で持続的な効果が期待できます。
「忌避剤って何?」って思いました?
簡単に言うと、ハクビシンが嫌がる匂いを出して近づかせない薬です。
でも、化学薬品だけじゃないんです。
実は身近な天然素材も大活躍。
まずは、効果的な忌避剤の種類を見てみましょう。
- 市販の動物用忌避スプレー
- 唐辛子やニンニクのすりおろし
- 柑橘系の果物の皮
- ハッカ油やペパーミントオイル
- 木酢液
特に天然素材は安全性が高いのがポイント。
子供やペットがいる家庭でも安心して使えます。
では、どう使えば効果的なのでしょうか?
使用方法のコツをご紹介します。
- ハクビシンの通り道に重点的に設置する
- 複数の種類を組み合わせて使う
- 定期的に新しいものと交換する
- 雨に濡れない場所を選ぶ
「よーし、たくさん撒いちゃえ!」なんて考えはNG。
強すぎる匂いは逆に人間が困っちゃいます。
適量を守りましょう。
具体的な使用例を見てみましょう。
例えば、「柑橘系の皮を乾燥させて、ハクビシンの侵入口付近に置く」「ニンニクをすりおろしてガーゼに包み、天井裏に吊るす」といった具合です。
「なるほど、こんな使い方があるんだ!」って感じですよね。
忌避剤の使用、少し面倒に感じるかもしれません。
でも、継続することで効果が出てきます。
「よし、毎週やってみよう!」その意気込みが大切です。
一緒に頑張りましょう!
「定期的な点検」で再侵入の兆候を早期発見!
定期的な点検は、ハクビシンの再侵入を防ぐ上で極めて重要です。早期発見が再被害を防ぐ鍵となります。
毎月の点検習慣をつけましょう。
「えっ、毎月点検?面倒くさそう…」なんて思いませんでしたか?
でも、これが実は一番の近道なんです。
小さな兆候を見逃さないことが、大きな被害を防ぐコツなんです。
では、どんなところをチェックすればいいのでしょうか?
ポイントをまとめてみました。
- 屋根や外壁の損傷や隙間
- 天井裏や床下の異音や臭い
- 庭や周辺の糞や足跡
- 果樹や野菜の食害跡
- 電線や配管の噛み跡
大丈夫、慣れれば10分程度で終わります。
点検の際は、こんな手順で行うのがおすすめです。
- まず、家の外周りを歩いてチェック
- 次に、屋根や軒下を双眼鏡で確認
- 天井裏や床下の様子を懐中電灯で調査
- 最後に、庭の植物や地面の状態を確認
「今月はここが気になったな」「先月と比べてこんな変化が…」といった具合に、変化を追えるようにしましょう。
ただし、注意点もあります。
高所作業は危険です。
「ちょっと屋根に上ってみよう」なんて無謀は禁物。
安全第一で行動しましょう。
もし、再侵入の兆候を見つけたらどうすればいいでしょうか?
慌てずに次の手順を踏みましょう。
- 写真を撮って記録する
- 被害が広がる前に応急処置をする
- 必要に応じて対策を強化する
定期点検、最初は面倒に感じるかもしれません。
でも、習慣になれば家の維持管理にもつながる大切な作業なんです。
「よし、来月から始めてみよう!」その意気込み、素晴らしいですね。
一緒に頑張りましょう!