ハクビシンが側溝から侵入?【直径15cm以上あれば可能】側溝からの侵入を防ぐ3つの効果的な方法

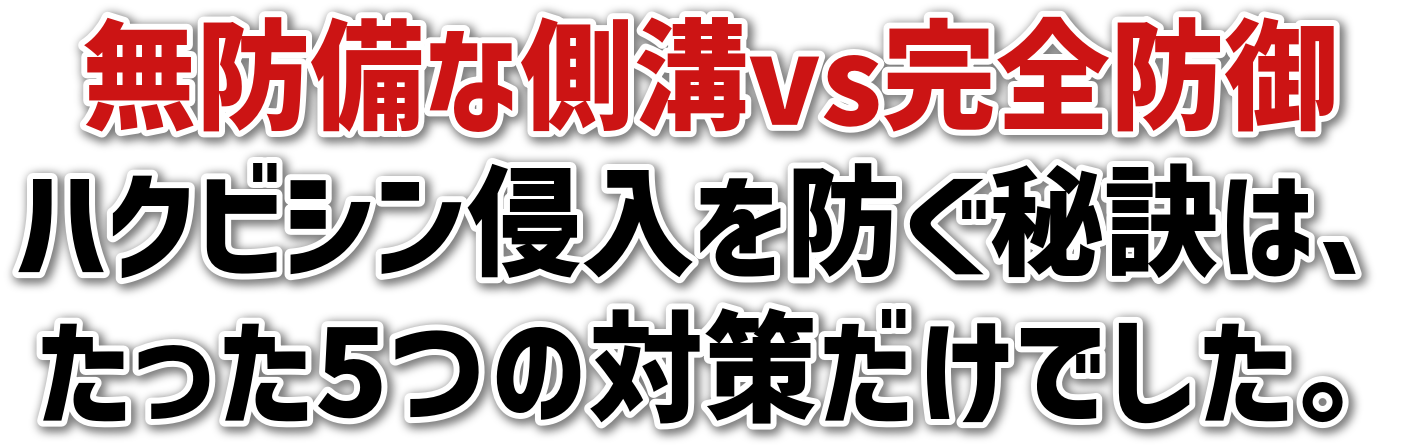
【この記事に書かれてあること】
側溝からハクビシンが侵入?- 側溝は直径15cm以上あればハクビシンの侵入経路に
- 側溝周辺は水と餌が豊富でハクビシンを引き寄せる
- 側溝の構造によって侵入しやすさが異なる
- 金属製グレーチングや細目ネットで物理的に侵入を防止
- 忌避剤や超音波装置を活用した効果的な対策法も
そんな悪夢のような話、実は現実なんです。
直径15センチ以上あれば、ハクビシンはすいすいと通り抜けてしまうんです。
「えっ、うちの側溝大丈夫?」そんな不安が頭をよぎりませんか?
でも安心してください。
この記事では、側溝からのハクビシン侵入を完全防御する5つの効果的な対策をご紹介します。
金属製グレーチングから超音波装置まで、あなたの家を守る最強の味方が見つかるはずです。
さあ、一緒にハクビシン対策の達人になりましょう!
【もくじ】
側溝からのハクビシン侵入リスク

側溝が侵入経路に!直径15cm以上なら「通過可能」
側溝は、思いがけないハクビシンの侵入経路になっています。直径15cm以上あれば、ハクビシンは楽々と通過できてしまうんです。
「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、ハクビシンは体を柔軟に曲げられる特徴があるんです。
見た目以上に細い隙間を通り抜けられる能力を持っているんです。
ハクビシンにとって、側溝は格好の通り道。
暗くて狭い空間は、天敵から身を隠すのに最適なんです。
さらに、側溝の中は比較的涼しいため、暑い季節には格好の移動ルートになっちゃうんです。
では、どんな側溝が危険なのでしょうか?
- U字型の深い側溝
- 蓋のない開放型の側溝
- 老朽化して隙間が広がった側溝
特に古い住宅街や田園地帯では、こういった側溝が多く存在します。
「うちの周りにもあるかも…」と心配になってきませんか?
側溝からの侵入を防ぐには、まずは自宅周辺の側溝をチェックすることが大切です。
直径15cm以上の開口部があれば、ハクビシンの侵入リスクが高いと考えましょう。
早めの対策が、家屋への被害を防ぐ鍵になるんです。
側溝周辺の魅力とは?水と餌が「豊富な生息地」に
側溝周辺は、ハクビシンにとって魅力たっぷりの場所なんです。なぜって?
水と餌が豊富な「ハクビシン天国」になっているからです。
まず、水の存在。
ハクビシンは水分補給や体温調整のために、定期的に水を必要とします。
側溝の中にたまった水は、彼らにとって貴重な水源なんです。
「ジャボジャボ」と水音を立てながら、のどの渇きを潤すハクビシンの姿が目に浮かびませんか?
次に、餌の豊富さ。
側溝周辺には、ハクビシンの大好物がたくさん!
- 落ち葉や腐葉土に集まる昆虫類
- 周辺の植物の果実や新芽
- 人間の食べ残しや生ゴミ
「いただきまーす!」とばかりに、側溝周辺で食事を楽しんでいるかもしれません。
さらに、側溝の構造自体が彼らの隠れ家にぴったり。
天敵から身を守りながら、食事や休憩ができる「安全地帯」になっているんです。
「こんなに居心地がいいなら、ずっと居着いちゃうかも…」そう考えるのもハクビシンの常。
一度居心地の良さを覚えると、なかなか離れてくれません。
側溝周辺の環境整備が、ハクビシン対策の第一歩。
水たまりをなくし、餌となる物を片付けることで、ハクビシンにとっての魅力を減らすことができるんです。
あなたの家の周りは大丈夫ですか?
今すぐチェックしてみましょう!
側溝を通る「小さな足音」に要注意!夜間の侵入増加
夜中に「とぽとぽ」という小さな足音が聞こえたら要注意です。それは、側溝を通ってハクビシンが侵入している証拠かもしれません。
夜間になると、ハクビシンの活動が活発になり、侵入のリスクが高まるんです。
ハクビシンは夜行性の動物。
日が沈むと行動を開始します。
特に、活動のピークは日没後2〜3時間。
この時間帯は最も警戒が必要です。
「みんなが寝静まった頃がチャンス!」とばかりに、ハクビシンは行動を始めるんです。
夜間に側溝を利用する理由は主に3つ。
- 人目につきにくい
- 天敵から身を守りやすい
- 涼しくて移動しやすい
「でも、うちは2階だから大丈夫じゃない?」なんて思っていませんか?
実は、ハクビシンは驚異的な運動能力の持ち主。
側溝から家屋へ、あっという間に登ってしまうんです。
夜間の侵入を防ぐには、以下の対策がおすすめです。
- センサーライトの設置
- 側溝の蓋をしっかり固定
- 家屋の周りに砂利を敷く
突然の明かりに驚いて、ハクビシンが逃げ出すことも多いんです。
夜中の小さな物音、侮ってはいけません。
それは、ハクビシンの侵入のサインかもしれないんです。
耳を澄ませて、早めの対策を心がけましょう。
あなたの家の平和は、夜の静けさの中で守られているんです。
側溝清掃を怠ると「被害拡大」のリスクが!定期的なケアを
側溝の清掃、ついつい後回しにしていませんか?実は、清掃を怠ると思わぬ被害拡大を招くかもしれないんです。
定期的なケアが、ハクビシン対策の要となります。
まず、清掃を怠るとどうなるでしょうか?
- 落ち葉や生ゴミが堆積
- 虫や小動物が増加
- 水たまりができやすい
「ごちそうさま〜」とばかりに、ハクビシンが側溝に集まってきてしまいます。
では、どのくらいの頻度で清掃すべきでしょうか?
季節や地域によって多少の違いはありますが、一般的に月1回程度が理想的です。
特に落ち葉の多い秋や、雨の多い梅雨時期は要注意。
こまめなチェックが大切です。
清掃時の注意点も押さえておきましょう。
- 手袋とマスクを必ず着用
- 長靴で足元を保護
- 熊手やブラシでしっかり掃除
- 集めたゴミは適切に処分
でも、側溝には思わぬ危険が潜んでいるんです。
ハクビシンの糞尿による感染症のリスクもあります。
安全第一で作業しましょう。
清掃後は、消毒もおすすめです。
薄めた塩素系漂白剤を使うと、衛生面でも安心です。
「きれいになった〜」という達成感と共に、ハクビシン対策も万全。
一石二鳥ですね。
定期的な側溝清掃は、快適な住環境を守るだけでなく、ハクビシンの被害から家を守る重要な一歩。
面倒くさがらずに、継続的なケアを心がけましょう。
あなたの努力が、家族の安全を守るんです。
側溝からの侵入を放置すると「大規模被害」に発展!
「まあ、ちょっとぐらいなら…」なんて、側溝からのハクビシン侵入を放置していませんか?実は、そんな油断が大規模被害につながる可能性があるんです。
早めの対策が、被害を最小限に抑える鍵なんです。
放置するとどんな被害が起こるのか、具体的に見てみましょう。
- 屋根裏や床下への住み着き
- 電線やケーブルの損傷
- 糞尿による悪臭や衛生問題
- 建材の破壊や劣化
- 家庭菜園や果樹への食害
「えっ、そんなに大変なの?」と驚く方も多いでしょう。
特に注意が必要なのが、電線やケーブルの損傷です。
ハクビシンは歯で様々なものを噛む習性があり、電線を噛み切ってしまうことも。
これが原因で火災のリスクも高まるんです。
ゾッとしませんか?
また、糞尿による被害も深刻です。
悪臭だけでなく、天井のシミの原因にもなります。
さらに、糞尿に含まれる細菌やウイルスによる健康被害のリスクも。
家族の健康が脅かされるかもしれません。
建材の破壊も見逃せません。
屋根裏や壁の中で巣作りを始めると、断熱材を掻き出したり、木材を噛んだりします。
これが進むと、家の構造自体に影響が出る可能性も。
「家が傷んじゃう…」なんてことにもなりかねません。
こうした被害を防ぐには、早期発見・早期対策が重要です。
側溝周辺の定期的なチェックや、不審な音や臭いがしたらすぐに調査するなど、常に警戒心を持つことが大切。
「我が家は大丈夫!」という自信を持てるよう、日頃からの備えを怠らないようにしましょう。
側溝の構造と侵入しやすさの比較
U字溝vs皿型側溝「どちらが危険?」侵入リスクを徹底比較
皿型側溝の方がU字溝よりもハクビシンに侵入されやすいんです。なぜなら、アクセスが容易だからです。
皿型側溝は、その名の通り浅い皿のような形をしています。
深さが浅いため、ハクビシンにとっては「どこからでも入れる」格好の侵入口になってしまうんです。
「これじゃあ、ハクビシンにとってはビュッフェみたいなもの!」と言えるでしょう。
一方、U字溝は深さがあるので、ハクビシンにとってはやや難易度が高くなります。
でも、油断は禁物!
ハクビシンは驚くほど器用なんです。
ではどちらの側溝が優れているのでしょうか?
それぞれの特徴を見てみましょう。
- U字溝:深さがあり、侵入しにくい。
排水能力が高い。 - 皿型側溝:浅いため侵入しやすいが、設置が簡単で価格が安い。
でも、ちょっと待ってください!
U字溝でも、蓋がなかったり隙間が大きいと、ハクビシンは簡単に侵入できてしまうんです。
結局のところ、どちらの側溝を選んでも、適切な対策が重要です。
例えば、細かい目のグレーチングを設置したり、定期的な清掃を行うことで、どちらの側溝でもハクビシンの侵入を防ぐことができます。
皆さんの家の周りにはどんな側溝がありますか?
今すぐチェックして、必要な対策を取りましょう。
ハクビシンに「お邪魔します〜」なんて言わせない、そんな側溝づくりを目指しましょう!
蓋付き側溝vs蓋なし側溝「安全性の差」は歴然!
蓋付き側溝の方が蓋なし側溝よりもハクビシンの侵入を防ぐ効果が高いんです。でも、それだけで安心はできません。
まず、蓋付き側溝のメリットを見てみましょう。
- ハクビシンの侵入を物理的に阻止
- 落ち葉や異物の侵入を防ぐ
- 人や車両の安全性が高い
蓋付きでも油断は禁物なんです。
なぜかって?
ハクビシンは驚くほど力持ちで器用なんです。
蓋と側溝の間に少しでも隙間があれば、そこを「てこ」にして蓋を持ち上げてしまうことがあるんです。
「えっ、そんなことまで!?」と驚く方も多いでしょう。
では、蓋なし側溝はどうでしょうか。
確かに、ハクビシンにとっては「いらっしゃいませ〜」状態。
でも、メリットがないわけではありません。
- 清掃が簡単
- 排水能力が高い
- 設置コストが低い
蓋付きなら、蓋をしっかり固定すること。
蓋なしなら、金網やネットを設置するなどの工夫が必要です。
例えば、蓋付き側溝でも、蓋と側溝の間に隙間テープを貼るという方法があります。
「ガムテープでいいの?」なんて思う方もいるかもしれませんが、専用の隙間テープを使うのがおすすめです。
蓋なし側溝の場合は、細かい目のグレーチングを設置するのが効果的。
「網戸みたいなもの?」そうです、でももっと頑丈なものを想像してください。
どちらの側溝を選んでも、定期的な点検と清掃を忘れずに。
「面倒くさいな〜」と思うかもしれませんが、これがハクビシン対策の基本なんです。
皆さんの家を守るため、しっかりと対策を立てましょう!
コンクリート製vs樹脂製「ハクビシンに好まれるのは?」
ハクビシンは樹脂製の側溝の方が好みます。なぜって?
表面が滑りにくく、爪が引っかかりやすいからなんです。
コンクリート製の側溝は、表面がツルツルしていることが多いんです。
ハクビシンにとっては「すべり台」のようなもの。
「よいしょ」っと登ろうとしても、ずるっと滑ってしまうんです。
一方、樹脂製の側溝は表面に細かい凹凸があることが多いんです。
これがハクビシンにとっては「天然のはしご」のような役割を果たしてしまうんです。
「よっこらしょ」と簡単に登れちゃうんです。
では、それぞれの特徴を比べてみましょう。
- コンクリート製:丈夫で長持ち、でも重くて設置が大変
- 樹脂製:軽くて設置が簡単、でもハクビシンに登られやすい
でも、そう単純ではないんです。
コンクリート製でも、表面が荒れてくると登りやすくなってしまいます。
「年月が経つと油断できないんだな」そうなんです。
定期的なメンテナンスが大切です。
樹脂製でも、表面に滑り止めスプレーを噴射するなどの対策を取れば、ハクビシンの侵入を防ぐことができます。
「まるで氷のスケートリンクみたい!」そんなイメージです。
どちらの素材を選んでも、適切な対策と定期的なケアが重要です。
例えば、側溝の上部に金属製のトゲを取り付けるのも効果的。
「痛そう!」そう、ハクビシンもそう思うはずです。
皆さんの家の側溝は何製ですか?
素材に合わせた対策を考えてみましょう。
ハクビシンに「ここは通れないよ〜」と思わせる、そんな側溝づくりを目指しましょう!
新旧側溝の比較!「古い側溝」ほど侵入リスクが高い?
古い側溝の方が新しい側溝よりもハクビシンの侵入リスクが高いんです。なぜそうなのか、詳しく見ていきましょう。
まず、古い側溝の特徴を考えてみましょう。
- 経年劣化による亀裂や隙間の増加
- 表面の摩耗によるざらつき
- 排水能力の低下による水たまりの形成
「えっ、そんなに違うの?」と思う方もいるでしょう。
例えば、亀裂や隙間。
ハクビシンは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。
「まるで忍者みたい!」そう、忍者のように器用なんです。
古い側溝の亀裂は、彼らにとって格好の侵入口になってしまうんです。
表面の摩耗も見逃せません。
新しい側溝ならツルツルしていても、古くなるとザラザラになってきます。
これが彼らの爪をひっかけるのに最適な状態になってしまうんです。
「まるで登山用のホールド」そんな感じです。
一方、新しい側溝はどうでしょうか。
- 表面が滑らかで登りにくい
- 隙間や亀裂が少ない
- 排水能力が高く、水たまりができにくい
でも、新しい側溝だからといって安心はできません。
時間が経てば古くなりますからね。
定期的なメンテナンスが大切です。
古い側溝をお持ちの方、がっかりしないでください。
補修や改修で対策は可能です。
例えば、亀裂を埋めたり、表面をコーティングしたりする方法があります。
「リフォームみたいだね」そう、側溝のリフォームなんです。
新旧にかかわらず、定期的な点検と清掃を忘れずに。
「面倒だな〜」と思うかもしれませんが、これがハクビシン対策の基本なんです。
みなさんの家を守るため、しっかりと対策を立てましょう!
排水性vs防御性「両立できる側溝」の特徴とは
排水性と防御性、両方を兼ね備えた側溝が理想的です。でも、これって本当に可能なんでしょうか?
実は、工夫次第で両立できるんです。
まず、排水性と防御性、それぞれの重要性を考えてみましょう。
- 排水性:雨水をスムーズに流し、水害を防ぐ
- 防御性:ハクビシンなどの小動物の侵入を防ぐ
どちらも欠かせない機能なんです。
では、両立のポイントは何でしょうか?
それは適切な設計と素材選びにあります。
例えば、グレーチング付きの側溝。
これなら排水性を保ちながら、ハクビシンの侵入も防げます。
「一石二鳥じゃん!」まさにその通りです。
グレーチングの目の細かさも重要です。
細すぎると排水性が落ちてしまいますが、粗すぎるとハクビシンが侵入してしまいます。
「難しいね〜」と思うかもしれませんが、専門家に相談すれば最適な設計を提案してくれますよ。
他にも、こんな工夫ができます。
- 側溝の深さを十分に確保し、排水能力を高める
- 側溝の壁面を滑らかにし、ハクビシンが登りにくくする
- 蓋と側溝の間に隙間テープを貼り、侵入を防ぐ
- 定期的な清掃で、排水能力を維持する
確かに初期投資は必要かもしれません。
でも、長い目で見れば、水害対策とハクビシン対策の両方ができるので、結果的にはお得なんです。
最後に、忘れてはいけないのが定期的なメンテナンスです。
どんなに優れた側溝でも、放っておけば機能が低下してしまいます。
「面倒くさいな〜」と思うかもしれませんが、これが側溝を長持ちさせるコツなんです。
皆さんの家の側溝は排水性と防御性、両方をしっかり備えていますか?
今すぐチェックして、必要な対策を取りましょう。
水害とハクビシン、両方から家を守る、そんな頼もしい側溝を目指しましょう!
側溝からのハクビシン侵入を防ぐ効果的な対策
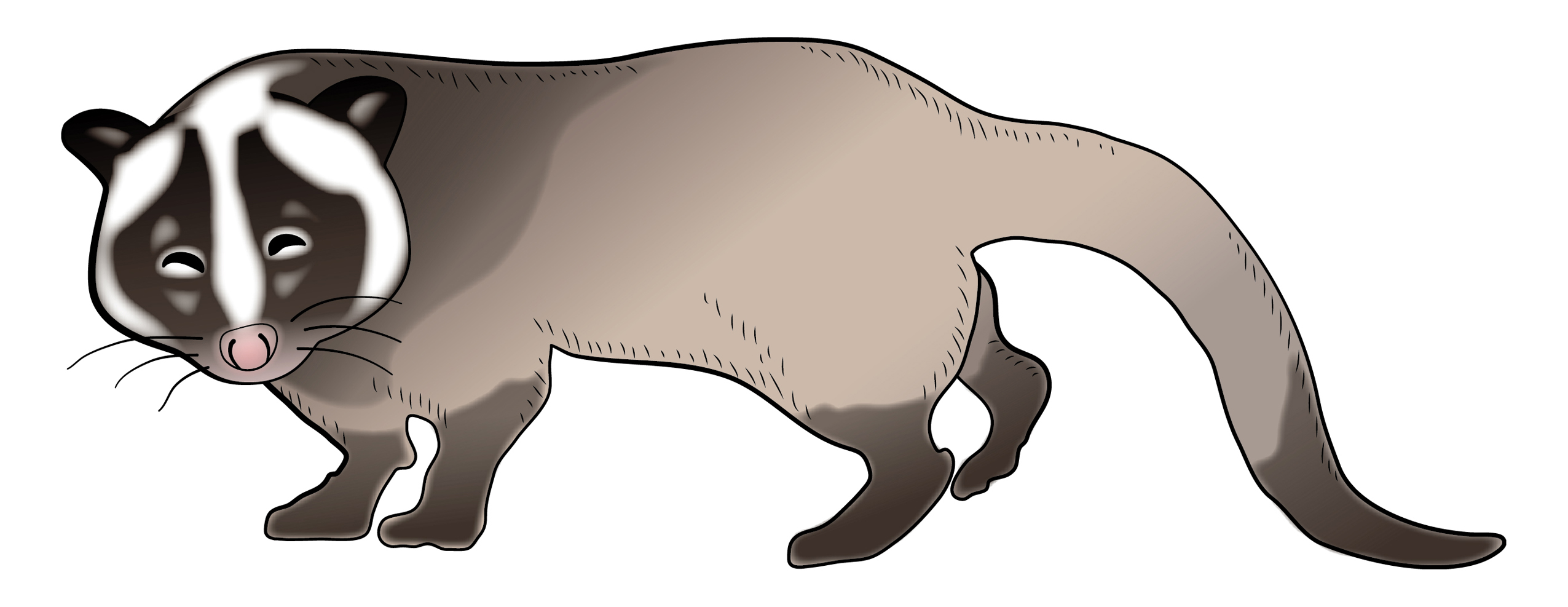
金属製グレーチングで「完全防御」!侵入を物理的に阻止
金属製グレーチングは、ハクビシンの侵入を物理的に阻止する強力な味方です。頑丈で耐久性が高く、長期的な防御策として最適なんです。
まず、金属製グレーチングの特徴を見てみましょう。
- 丈夫で壊れにくい
- 隙間を細かく調整できる
- 長期間使用可能
- 見た目もスッキリ
実は、金属製グレーチングはハクビシン対策の王様とも言えるんです。
金属製グレーチングの隙間は、通常5センチ以下に設計されています。
ハクビシンは驚くほど体を柔軟に曲げられますが、それでも5センチ以下の隙間は通過できないんです。
「まるで鉄壁の要塞みたい!」そう、まさにその通りなんです。
設置の際は、側溝全体をしっかりカバーすることが重要です。
「ちょっとぐらいいいか」なんて思わないでください。
ハクビシンは賢い動物なので、少しでも隙があれば見つけ出してしまうんです。
ただし、注意点もあります。
金属製グレーチングは重いので、設置には力が必要です。
「うーん、ちょっと大変そう...」と思う方もいるでしょう。
そんな時は、家族や友人に手伝ってもらうのもいいですね。
みんなで力を合わせれば、きっと楽しく作業できるはずです。
また、定期的な点検も忘れずに。
錆びていないか、隙間が広がっていないかをチェックしましょう。
「面倒くさいなぁ」と思うかもしれませんが、これが長期的な防御につながるんです。
金属製グレーチングで、ハクビシンに「ここは通れないよ」とはっきり伝えましょう。
あなたの家を守る強力な味方になってくれるはずです。
細目ネットを活用!「15cm以下」の隙間を徹底カバー
細目ネットは、ハクビシン対策の中でも特に使いやすく効果的な方法です。15センチ以下の隙間をしっかりカバーして、ハクビシンの侵入を防ぐんです。
細目ネットの魅力は、なんといってもその使いやすさ。
金属製グレーチングほど重くないので、一人でも簡単に設置できるんです。
「よっこらしょ」と言いながら作業する必要もありません。
では、細目ネットの特徴を見てみましょう。
- 軽量で扱いやすい
- 柔軟性があり、様々な形状に対応
- 価格が比較的安い
- 必要に応じて切り取りや継ぎ足しが可能
細目ネットを選ぶ際は、目の細かさがポイントです。
ハクビシンが通り抜けられないよう、1.5センチ角程度の目の細かさを選びましょう。
「虫よけネットみたいだね」そう、イメージはそんな感じです。
設置する際は、側溝全体をしっかりカバーすることが大切です。
端っこや隅っこまでしっかり覆いましょう。
「ちょっとぐらいいいか」なんて思わないでくださいね。
ハクビシンは賢いので、少しでも隙間があれば見つけ出してしまうんです。
ただし、細目ネットにも弱点があります。
風で飛ばされやすかったり、鋭利な物で破れやすかったりするんです。
「えっ、そんな弱いの?」と不安になる方もいるでしょう。
でも大丈夫。
定期的にチェックして、必要に応じて補修や交換をすれば問題ありません。
また、細目ネットは見た目もスッキリしているので、景観を損なう心配もありません。
「見た目も大事だよね」そう思う方にもおすすめです。
細目ネットで、ハクビシンに「ここは立ち入り禁止エリアだよ」とやさしく、でもしっかり伝えましょう。
あなたの家を守る頼もしい味方になってくれるはずです。
側溝周辺に「忌避剤」を設置!効果的な使用法と注意点
忌避剤は、ハクビシンを寄せ付けない臭いや味で侵入を防ぐ効果的な方法です。でも、使い方を間違えると効果が半減してしまうんです。
正しい使用法と注意点をしっかり押さえましょう。
まず、忌避剤の特徴を見てみましょう。
- 強い臭いや味でハクビシンを遠ざける
- 設置が簡単
- 比較的安価
- 即効性がある
忌避剤の種類は様々ですが、主に粒状タイプとスプレータイプがあります。
粒状タイプは側溝周辺にまくだけ、スプレータイプは直接吹きかけるだけと、どちらも使い方は簡単です。
「子供でも使えそう!」そう、本当に簡単なんです。
ただし、効果を最大限に発揮させるには、いくつかのコツがあります。
- 定期的に補充する(雨で流れたり、効果が薄れたりするため)
- ハクビシンの通り道全体に設置する
- 天候や季節に応じて使用量を調整する
でも、これらのポイントを押さえることで、忌避剤の効果を最大限に引き出せるんです。
注意点もいくつかあります。
まず、人体や他の動物への影響です。
強い臭いのものもあるので、使用する場所には気を付けましょう。
また、植物に直接かけると枯れてしまう可能性もあります。
「危険じゃない?」と心配になる方もいるでしょう。
でも、使用上の注意をしっかり守れば問題ありません。
また、忌避剤だけに頼りすぎるのも禁物です。
物理的な防御策と組み合わせることで、より効果的なハクビシン対策になります。
「ダブルで守る」というわけです。
忌避剤で、ハクビシンに「この場所は居心地が悪いよ」とやさしく伝えましょう。
正しく使えば、あなたの家を守る強力な味方になってくれるはずです。
ペパーミントの香りで撃退!「天然ハクビシン対策」の秘訣
ペパーミントの香りは、ハクビシン対策の中でも特に環境にやさしい方法です。強い香りでハクビシンを寄せ付けず、しかも人間にとっては心地よい香りなんです。
まず、ペパーミントを使ったハクビシン対策の特徴を見てみましょう。
- 自然由来なので安心安全
- 人間には心地よい香り
- 植物なので見た目も◎
- 長期的に使える
ペパーミントを使う方法はいくつかあります。
生の植物を植える、精油を使う、ペパーミント入りの市販の忌避剤を使うなどです。
どの方法を選ぶかは、あなたの好みや環境に合わせて決めましょう。
生の植物を植える場合は、側溝周辺に植えるのがおすすめです。
「まるでハーブガーデンみたい!」そう、見た目も楽しめるんです。
ただし、ペパーミントは繁殖力が強いので、広がりすぎないように注意が必要です。
精油を使う場合は、綿球に数滴たらして側溝周辺に置くといいでしょう。
「お部屋の芳香剤みたいだね」そう、使い方は簡単です。
ただし、雨で流されやすいので、定期的な補充が必要です。
市販の忌避剤を使う場合は、使用方法をしっかり守ることが大切です。
効果を最大限に引き出すためには、正しい使い方が欠かせません。
ただし、ペパーミントだけに頼りすぎるのは禁物です。
他の対策方法と組み合わせることで、より効果的なハクビシン対策になります。
「いろんな方法を組み合わせるんだね」そう、多角的なアプローチが大切なんです。
また、効果には個体差があることも覚えておきましょう。
「うちのハクビシンは強敵かも...」なんて思うこともあるかもしれません。
そんな時は、他の対策方法も試してみるのがいいでしょう。
ペパーミントの香りで、ハクビシンに「ここは居心地が悪いよ」とやさしく伝えましょう。
あなたの家を守る、香り高い味方になってくれるはずです。
超音波装置で「音」による対策!静かで効果的な防御法
超音波装置は、人間には聞こえない高周波音でハクビシンを撃退する、静かで効果的な防御法です。音で対策するなんて不思議に思えるかもしれませんが、実はとても優れた方法なんです。
まず、超音波装置の特徴を見てみましょう。
- 人間には聞こえない音なので静か
- 電気で動くので長期的に使用可能
- 設置が簡単
- 薬品を使わないので環境にやさしい
超音波装置は、人間には聞こえない高周波音を発生させます。
この音は、ハクビシンにとってはとても不快なんです。
「まるで耳をふさぎたくなるような音かな」そう、ハクビシンにとってはそんな感じなんです。
設置場所は、側溝周辺や庭、家の周りなど、ハクビシンが侵入しそうな場所がおすすめです。
電源が必要なので、コンセントの位置も考慮しましょう。
「えっ、外にコンセント?」と思う方もいるかもしれません。
その場合は、屋外用の延長コードを使うのも一つの手です。
ただし、超音波装置にも注意点があります。
まず、効果範囲です。
壁や物に遮られると効果が弱くなってしまうので、なるべく障害物のない場所に設置しましょう。
また、他のペットへの影響も考慮する必要があります。
「うちの犬や猫は大丈夫かな?」と心配になる方もいるでしょう。
多くの場合は問題ありませんが、念のため使用前に確認するのがいいでしょう。
また、効果には個体差があることも覚えておきましょう。
「うちのハクビシンは音に強いのかも...」なんて思うこともあるかもしれません。
そんな時は、他の対策方法と組み合わせるのがおすすめです。
超音波装置は、24時間365日休まず働いてくれる頼もしい味方です。
でも、たまには動作確認をするのを忘れずに。
「黙々と働いてくれてありがとう」なんて声をかけてあげるのもいいかもしれませんね。
超音波装置で、ハクビシンに「ここは居心地が悪いよ」と静かに、でもしっかり伝えましょう。
あなたの家を守る、頼もしい味方になってくれるはずです。