ハクビシンの侵入経路はどこ?【屋根裏が最多】家屋の弱点5か所と封鎖法を解説

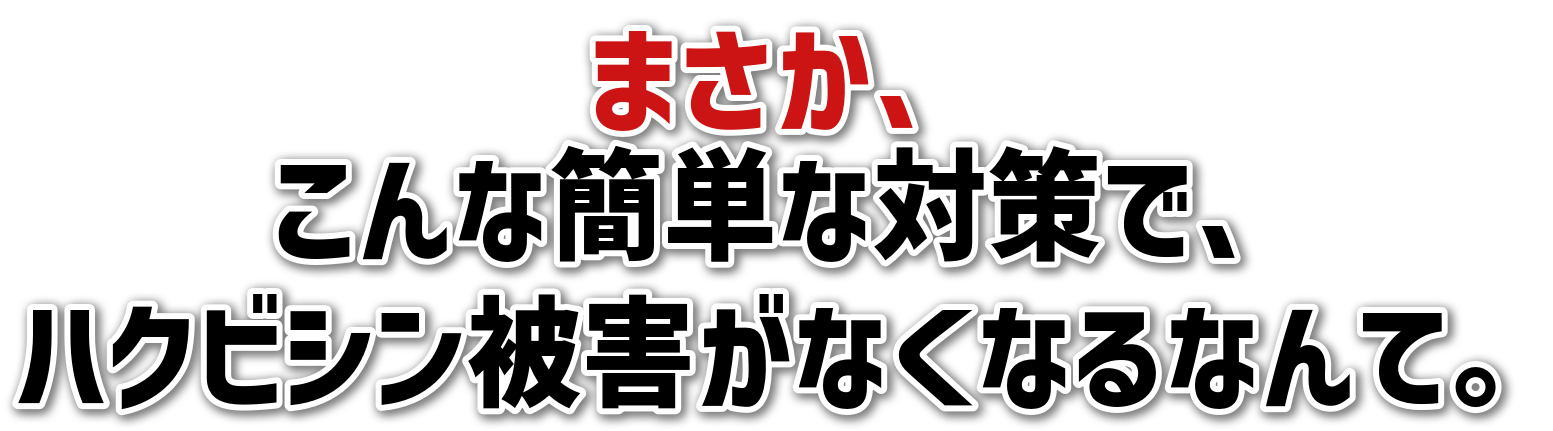
【この記事に書かれてあること】
「ガサガサ」「カリカリ」…夜中に聞こえる不気味な音。- ハクビシンはわずか5cmの隙間から侵入可能
- 屋根裏が最多の侵入経路で被害拡大のリスクあり
- 換気口や排水管など複数の侵入経路に要注意
- 侵入跡の見分け方は爪痕・糞尿・異臭がポイント
- 経路別の効果的な対策で被害を防止
ハクビシンが家に侵入している可能性があります。
でも、どこから入ってくるの?
実は、ハクビシンは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。
屋根裏が最多の侵入経路ですが、他にも様々な経路があります。
この記事では、ハクビシンの主な侵入経路と、効果的な対策方法を詳しく解説します。
家族の安全と快適な暮らしを守るため、一緒にハクビシン対策を学んでいきましょう!
【もくじ】
ハクビシンの侵入経路「屋根裏最多」の実態

わずか5cmの隙間から侵入!ハクビシンの驚異的な能力
ハクビシンは驚くほど小さな隙間から家に侵入できるんです。なんと、たった5cmの隙間があれば十分なのです!
「えっ、5cmってスマートフォンの幅くらい?」そう思った方も多いはず。
でも、本当なんです。
ハクビシンの体は柔軟で、まるでゴムのように伸び縮みします。
この特徴を活かして、信じられないほど小さな隙間をすり抜けてしまうのです。
ハクビシンの侵入能力を例えると、こんな感じです。
- 細いストローを通り抜ける水滴のように、体を細くして隙間を通り抜ける
- 折り紙のように体を折りたたみ、小さな空間に収まる
- 伸縮性のあるゴムボールのように、体を自在に変形させる
屋根裏、換気口、排水管…どこでも侵入口になりうるのです。
「うちは隙間なんてないはず!」そう思っても油断は禁物。
ハクビシンの目には、私たちが気づかない小さな隙間も大きな侵入口に見えているかもしれません。
家の周りをよく観察し、小さな隙間も見逃さないようにしましょう。
ハクビシン対策の第一歩は、この驚異的な侵入能力を理解することなんです。
屋根裏が最多の理由「静かで安全な居場所」に注目
ハクビシンが家に侵入する際、最も多く選ぶのが屋根裏なんです。なぜ屋根裏なのか、その理由を見ていきましょう。
まず、屋根裏は静かで安全な居場所なんです。
人の気配が少なく、外敵から身を隠すのに最適なんです。
「まるで秘密基地みたいだね」と思うかもしれません。
そう、ハクビシンにとっては理想的な隠れ家なんです。
屋根裏が選ばれる理由は他にもあります。
- 温度が安定していて快適
- 雨風をしのげる絶好の場所
- 子育てに適した環境
- 餌探しに出かけやすい
実は、屋根と壁の接合部や軒下の隙間など、私たちが気づきにくい場所から侵入するんです。
ハクビシンの視点で家を見てみると、「あそこから入れそう!」という場所がたくさん見つかるかもしれません。
屋根裏に住み着かれると、天井裏を走り回る音や、糞尿による悪臭など、様々な問題が発生します。
「ドタドタ」「カサカサ」という音が聞こえたら要注意。
早めの対策が大切です。
屋根裏をハクビシンに占拠されないためには、定期的な点検と隙間の封鎖が効果的です。
家の周りをよく観察し、小さな隙間も見逃さないようにしましょう。
屋根裏を安全に保つことで、ハクビシンの侵入を防ぐことができるんです。
換気口からの侵入「直接室内へ」で被害拡大の危険性
換気口からのハクビシンの侵入は、特に警戒が必要です。なぜなら、直接室内へ侵入できてしまうからなんです。
換気口は新鮮な空気を取り入れる大切な役割がありますが、同時にハクビシンにとっては格好の侵入経路になってしまいます。
「えっ、そんな小さな穴から入れるの?」と驚くかもしれません。
でも、ハクビシンの驚異的な身体能力を考えると、十分に可能なんです。
換気口からの侵入が危険な理由をまとめてみましょう。
- 室内に直接アクセスできるため、家財の被害が大きい
- 食べ物を荒らされる可能性が高い
- 糞尿による衛生面のリスクが深刻
- 人やペットとの接触機会が増え、感染症のリスクも
もしかしたら、ハクビシンが侵入しようとしているかもしれません。
対策としては、換気口にステンレス製の網を取り付けるのが効果的です。
ただし、通気性を妨げないよう注意が必要です。
「網を付けたら換気できなくなっちゃうんじゃない?」そんな心配は無用です。
適切な網を選べば、空気の流れを確保しながらハクビシンの侵入を防げるんです。
換気口の定期的な点検も大切です。
破損や歪みがないか、こまめにチェックしましょう。
小さな隙間も見逃さないよう、慎重に観察することがポイントです。
換気口をしっかり守ることで、ハクビシンの侵入を防ぎ、安全な住環境を維持できるんです。
排水管侵入は要注意!「配管損傷」のリスクも
排水管からのハクビシンの侵入は、見落としがちですが重大な問題を引き起こす可能性があるんです。なぜなら、配管を損傷させるリスクがあるからです。
ハクビシンは水辺を好む性質があり、湿気のある排水管は格好の侵入経路になってしまいます。
「え?排水管って細くないの?」そう思うかもしれません。
でも、ハクビシンの柔軟な体を考えると、十分に通り抜けられるんです。
排水管侵入のリスクをまとめてみましょう。
- 配管を噛んだり引っ掻いたりして損傷させる
- 排水の流れを妨げ、水漏れや逆流の原因に
- 悪臭の原因になる
- 衛生面でのリスクが高い
- 繁殖場所として利用される可能性がある
対策としては、排水口にステンレス製の網や逆流防止弁を取り付けるのが効果的です。
「網を付けたら排水が詰まらない?」心配無用です。
適切な網を選べば、水の流れを妨げずにハクビシンの侵入を防げるんです。
また、排水管の周りに使用済みのコーヒー粕を撒くのも効果的です。
強い香りでハクビシンを寄せ付けません。
定期的な排水管の点検も忘れずに。
小さな損傷も見逃さないよう、注意深く観察することが大切です。
排水管をしっかり守ることで、ハクビシンの侵入を防ぎ、家全体の衛生状態を保つことができるんです。
油断は禁物、こまめなチェックを心がけましょう。
侵入経路を放置すると「家屋全体に被害が拡大」!
ハクビシンの侵入経路を放置すると、とんでもないことになってしまうんです。なんと、家屋全体に被害が広がっていくんです。
「えっ、そんなに深刻なの?」と思うかもしれません。
でも、本当に大変なことになるんです。
ハクビシンは一度居心地の良い場所を見つけると、そこを拠点にどんどん活動範囲を広げていきます。
その結果、家全体が「ハクビシンハウス」になってしまうんです。
被害が拡大していく様子を想像してみましょう。
- 屋根裏から天井裏全体に生活範囲が広がる
- 壁の中を自由に移動し、家中を縦横無尽に走り回る
- 電気配線を噛み切り、火災の危険性が高まる
- 断熱材を巣材として使用し、家の断熱性能が低下
- 糞尿による悪臭が家中に充満
最悪の場合、家の構造自体が弱くなり、大規模な修繕が必要になることも。
修理費用は数十万円から、ひどい場合は数百万円にもなりかねません。
「そんなお金、出せないよ!」ですよね。
だからこそ、早めの対策が重要なんです。
侵入経路を見つけたら、すぐに適切な方法で塞ぎましょう。
ただし、やみくもに塞ぐのは危険です。
中にハクビシンが閉じ込められる可能性があるからです。
専門家に相談するのが最も安全で確実な方法です。
家全体の定期的な点検も忘れずに。
小さな変化も見逃さないよう、注意深く観察することが大切です。
侵入経路をしっかり防ぐことで、ハクビシンによる被害から家を守り、安全で快適な住環境を維持できるんです。
侵入経路の発見と効果的な対策方法
屋根裏vs換気口「侵入跡の発見しやすさ」を比較
屋根裏と換気口、どちらの侵入跡が見つけやすいでしょうか?結論から言うと、換気口の方が発見しやすいんです。
「えっ、そうなの?」と思った方も多いはず。
でも、考えてみれば納得できますよね。
換気口は家の外から目視できる場所にあることが多いんです。
一方、屋根裏は普段あまり立ち入らない場所ですからね。
では、具体的にどんな違いがあるのか見ていきましょう。
- 換気口:外から見える位置にあり、グリルの変形や破損がすぐに分かる
- 屋根裏:天井裏にあるため、日常的に確認するのが難しい
- 換気口:周囲の爪痕や毛、異臭などが気づきやすい
- 屋根裏:侵入跡を見つけるには、わざわざ屋根裏に上がる必要がある
確かにその通りです。
しかし、物音だけでは侵入経路を特定するのは難しいんです。
例えば、屋根裏で「ガサガサ」という音がしたとしましょう。
これだけでは、ハクビシンがどこから侵入したのかまでは分かりません。
一方、換気口のグリルが曲がっていたら、そこが侵入口だと特定しやすいですよね。
ただし、注意点があります。
換気口が見つけやすいからといって、屋根裏の点検をおろそかにしてはいけません。
なぜなら、屋根裏は被害が大きくなりやすい場所だからです。
定期的に屋根裏をチェックする習慣をつけましょう。
侵入跡の発見しやすさを知ることで、効果的な対策が立てられます。
換気口は日々の観察を、屋根裏は定期的な点検を心がけることが大切です。
こうすることで、ハクビシンの侵入を早期に発見し、被害を最小限に抑えられるんです。
屋根裏vs排水管「被害の深刻度」はどちらが高い?
屋根裏と排水管、どちらの被害が深刻なのでしょうか?結論から言うと、屋根裏の方が被害の深刻度が高いんです。
「えっ、排水管の方が大変そうじゃない?」と思う方もいるかもしれません。
確かに排水管の被害も深刻ですが、屋根裏の被害は家全体に影響を及ぼす可能性が高いんです。
では、具体的にどんな違いがあるのか、被害の特徴を見てみましょう。
- 屋根裏:電気配線の損傷で火災のリスクが高まる
- 排水管:配管の損傷で水漏れの可能性がある
- 屋根裏:断熱材の破壊で冷暖房効率が悪化し、光熱費が上昇
- 排水管:詰まりや逆流で不衛生な状態になる
- 屋根裏:糞尿による天井のシミや悪臭が家全体に広がる
- 排水管:局所的な臭いの問題が発生する
屋根裏は家の中でも特に重要な場所なんです。
ここが被害を受けると、修理費用も高額になりがちです。
例えば、屋根裏の電気配線をハクビシンが噛んでしまったとしましょう。
これは火災の原因になる可能性があるんです。
「ゾッ」としませんか?
一方、排水管の被害は主に水回りの問題ですから、比較的対処しやすいんです。
ただし、注意点があります。
排水管の被害を軽視してはいけません。
排水管の問題も、放っておくと深刻化する可能性があるんです。
例えば、配管の損傷が進むと、修理に大がかりな工事が必要になることも。
被害の深刻度を理解することで、優先順位をつけた対策が立てられます。
屋根裏の対策を最優先にしつつ、排水管も定期的にチェックすることが大切です。
こうすることで、ハクビシンによる被害を最小限に抑え、安心して暮らせる家を守れるんです。
壁の隙間vs樋「見つけにくさ」で勝負!
壁の隙間と樋、どちらのハクビシン侵入経路が見つけにくいでしょうか?結論から言うと、壁の隙間の方が見つけにくいんです。
「えっ、そうなの?」と思った方も多いはず。
でも、よく考えてみれば納得できますよね。
樋は家の外側にあって目につきやすいですが、壁の隙間は見えにくい場所にあることが多いんです。
では、具体的にどんな違いがあるのか見ていきましょう。
- 壁の隙間:家の内部にあり、日常的に目につきにくい
- 樋:家の外側にあり、外から確認しやすい
- 壁の隙間:小さな穴や亀裂を見つけるのが難しい
- 樋:ハクビシンの爪痕や破損が比較的分かりやすい
- 壁の隙間:内装に隠れていることもあり、発見が遅れがち
- 樋:雨の日に水漏れなどの異常が見つかりやすい
確かにその通りです。
しかし、音がするからといって、すぐに侵入口が特定できるわけではないんです。
例えば、壁の中で「カサカサ」という音がしたとしましょう。
これだけでは、ハクビシンがどこから侵入したのかまでは分かりません。
一方、樋に爪痕があったり、樋の継ぎ目が外れていたりしたら、そこが侵入口だと特定しやすいですよね。
ただし、注意点があります。
樋が見つけやすいからといって、壁の点検をおろそかにしてはいけません。
壁の隙間からの侵入は、家の構造に大きなダメージを与える可能性があるんです。
定期的に壁をチェックする習慣をつけましょう。
見つけにくさを知ることで、より注意深い点検ができます。
壁の隙間は特に念入りに、樋は日々の観察を心がけることが大切です。
こうすることで、ハクビシンの侵入を早期に発見し、被害を最小限に抑えられるんです。
家を守るためには、見えない敵にも注意を払う必要があるんです。
侵入経路別「最適な封鎖材料」一覧
ハクビシンの侵入を防ぐには、経路に合わせた適切な封鎖材料を選ぶことが重要です。ここでは、主な侵入経路ごとの最適な封鎖材料をご紹介します。
「どの材料を使えばいいの?」と迷っている方も多いはず。
大丈夫です。
経路ごとに最適な材料があるんです。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
- 屋根裏:金属製のメッシュや板、膨張ウレタンフォーム
- 換気口:通気性のある金属製のカバー
- 排水管:ステンレス製のネットや逆流防止弁
- 壁の隙間:スチールウール、金属板
- 樋:金属製の補強材、目の細かい金網
それぞれの経路に合わせて材料を選ぶことで、より効果的な対策ができるんです。
例えば、屋根裏の場合は金属製のメッシュが効果的です。
なぜなら、ハクビシンの鋭い歯や爪にも耐えられる強度があるからです。
一方、換気口の場合は通気性を確保しつつ侵入を防ぐ必要があるので、通気性のある金属製カバーが最適なんです。
ただし、注意点があります。
材料を選ぶ際は、見た目や価格だけでなく、耐久性や施工のしやすさも考慮しましょう。
例えば、屋外で使用する材料は耐候性のあるものを選ぶ必要があります。
また、封鎖材料を取り付ける際は、ハクビシンが中にいないことを確認してから行いましょう。
「もし中にいたらどうしよう…」と心配になりますよね。
そんな時は、音や光で追い出してから封鎖するのがおすすめです。
適切な封鎖材料を使うことで、ハクビシンの侵入をしっかり防ぐことができます。
家を守るための投資だと思って、質の良い材料を選びましょう。
こうすることで、長期的にはコストを抑えつつ、安心して暮らせる環境を作れるんです。
侵入跡の見分け方「爪痕・糞尿・異臭」に注目!
ハクビシンの侵入跡を早期に発見するのは、被害を最小限に抑える重要なポイントです。ここでは、侵入跡を見分けるための3つの重要なサインをご紹介します。
「え、侵入跡ってどうやって見つけるの?」と思う方も多いはず。
大丈夫です。
ハクビシンは必ず痕跡を残すんです。
その痕跡を知れば、早期発見につながります。
では、具体的にどんなサインに注目すればいいのか見ていきましょう。
- 爪痕:木材や壁に残る細い引っかき傷
- 糞尿:小さな黒い糞や黄色っぽいシミ
- 異臭:獣特有の強烈な臭い
これらのサインを見逃さないことが、早期発見のカギなんです。
例えば、屋根裏の木材に細い引っかき傷を見つけたとしましょう。
これはハクビシンの爪痕かもしれません。
「ゾクッ」としますよね。
また、天井に黄色っぽいシミを見つけたら、それはハクビシンの尿の痕跡かもしれないんです。
ただし、注意点があります。
これらのサインは他の動物でも似たようなものが見られることがあります。
そのため、複数のサインを総合的に判断することが大切です。
「でも、どうやって確認するの?」という疑問も出てくるでしょう。
定期的な点検がポイントです。
特に、屋根裏や壁の隙間、換気口の周りなど、ハクビシンが好む場所を重点的にチェックしましょう。
侵入跡を早期に発見できれば、被害が広がる前に対策を取ることができます。
「ガサガサ」という音や「プンプン」という臭いがしたら要注意。
すぐにチェックして、必要な対策を講じましょう。
こうした習慣をつけることで、ハクビシンの侵入を未然に防ぎ、安心して暮らせる家を守ることができるんです。
家族の安全と快適な生活のために、ちょっとした心がけが大切なんです。
ハクビシン撃退!驚きの裏技と注意点

屋根裏侵入を防ぐ「小麦粉大作戦」で足跡を追え!
屋根裏のハクビシン侵入を防ぐ裏技として、小麦粉を使った足跡追跡法が効果的です。「え?小麦粉?お菓子作りじゃないんだけど…」と思った方、びっくりしましたよね。
でも、これが意外と役立つんです。
小麦粉大作戦の手順を見てみましょう。
- 屋根裏の床に薄く小麦粉を撒く
- 翌朝、小麦粉の上についた足跡を確認
- 足跡をたどって侵入口を特定
- 見つかった侵入口を適切に封鎖
ハクビシンの足跡が小麦粉の上にくっきり残るので、侵入経路が一目瞭然なんです。
ただし、注意点もあります。
小麦粉を撒きすぎると、ハクビシンが警戒して近づかなくなる可能性があります。
また、湿気が多い場所では小麦粉が固まってしまうかもしれません。
「でも、小麦粉って掃除が大変そう…」という心配も出てくるでしょう。
確かにその通りです。
でも、侵入口を見つけられれば、その後の対策がぐっと楽になるんです。
一時的な手間と引き換えに、長期的な安心を手に入れられると考えてみてはどうでしょうか。
この方法は、まるで探偵のように足跡を追うようでワクワクしますよね。
子供と一緒に「ハクビシン探偵団」ごっこをしながら、家族で協力して対策を立てるのも楽しいかもしれません。
小麦粉大作戦で侵入口を見つけたら、すぐに適切な方法で封鎖しましょう。
ただし、ハクビシンが中にいないことを確認してからですよ。
これで、屋根裏のハクビシン対策が一歩前進します。
家族みんなで安心して暮らせる日も、そう遠くないはずです。
換気口に「ペパーミントオイル」でハクビシン撃退!
換気口からのハクビシン侵入を防ぐ意外な裏技として、ペパーミントオイルの活用が注目されています。「えっ、ハッカ油でハクビシン撃退?」と思った方も多いはず。
でも、これが意外と効果的なんです。
ペパーミントオイルを使った撃退法の手順を見てみましょう。
- ペパーミントオイルを水で薄める(10倍程度に希釈)
- 霧吹きに入れて換気口の周りに吹きかける
- 換気口のそばに、オイルを染み込ませた布を置く
- 定期的に(週に1〜2回程度)繰り返す
ハクビシンは強い香りが苦手で、特にペパーミントの香りを嫌うんです。
この香りで寄せ付けない効果が期待できるんです。
ただし、注意点もあります。
原液を直接使うと刺激が強すぎる可能性があるので、必ず希釈してください。
また、換気口の機能を妨げないよう、適量の使用を心がけましょう。
「でも、家中がミント臭くならない?」という心配も出てくるでしょう。
確かにその通りです。
でも、ハクビシンにとっては強烈な臭いでも、人間にとっては心地よい香りになることが多いんです。
むしろ、家の中が爽やかになるかもしれませんよ。
この方法は、まるでアロマテラピーをしているかのようですね。
家族で好みの香りを選んでみるのも楽しいかもしれません。
「今日の香りは何にする?」なんて会話が増えるかも。
ペパーミントオイルでハクビシン対策をしながら、家族の絆も深まる。
一石二鳥ですね。
ただし、効果には個体差があるので、様子を見ながら他の対策と組み合わせるのがおすすめです。
これで、換気口からのハクビシン侵入の心配が少し減るはずです。
爽やかな香りに包まれた、安心な暮らしを手に入れましょう。
排水管侵入阻止「使用済み猫砂」で天敵の匂い演出
排水管からのハクビシン侵入を防ぐ意外な裏技として、使用済みの猫砂の活用が効果的です。「えっ、使用済みの猫砂?ちょっと気持ち悪いなぁ…」と思った方も多いはず。
でも、これがハクビシン対策には大活躍するんです。
猫砂を使った撃退法の手順を見てみましょう。
- 使用済みの猫砂を小さな布袋に入れる
- その布袋を排水管の周りに置く
- 雨で濡れないよう、屋根のある場所を選ぶ
- 1週間に1回程度、新しいものと交換する
ハクビシンにとって、猫は天敵の一つなんです。
猫の匂いがする場所には近づきたくないという本能があるんです。
ただし、注意点もあります。
使用済みの猫砂を直接まくのは衛生面で問題があるので、必ず布袋などに入れましょう。
また、近所の猫が寄ってくる可能性もあるので、置き場所には気を付けてください。
「でも、臭くならない?」という心配も出てくるでしょう。
確かにその通りです。
でも、布袋に入れることで臭いは抑えられますし、排水管の周りという限られた場所での使用なので、そこまで気にならないはずです。
この方法は、まるで「猫の縄張り作戦」のようですね。
実際に猫を飼っていなくても、猫カフェに行って使用済みの猫砂をもらってくるのも一案かもしれません。
「今日は猫砂ゲットの日!」なんて、新しい習慣が増えるかも。
使用済み猫砂でハクビシン対策をしながら、実は猫好きだったという家族の意外な一面を発見するかもしれません。
思わぬ効果で家族の会話が増えるなんて、素敵ですね。
ただし、猫アレルギーの方がいる家庭では使用を控えましょう。
これで、排水管からのハクビシン侵入の心配が少し減るはずです。
家族みんなで協力して、安心な暮らしを手に入れましょう。
壁の隙間に「スチールウール」で完璧ガード!
壁の隙間からのハクビシン侵入を防ぐ効果的な方法として、スチールウールの活用が注目されています。「スチールウール?食器洗いのアレ?」と思った方、正解です!
でも、ハクビシン対策にも大活躍するんです。
スチールウールを使った防御法の手順を見てみましょう。
- 壁の隙間の大きさを確認する
- スチールウールを隙間よりやや大きめに切る
- 隙間にスチールウールをしっかり詰め込む
- 外側を防水性のある材料で覆う
スチールウールの細かい金属繊維が、ハクビシンの鋭い歯や爪を寄せ付けないんです。
噛んだり引っ掻いたりしようとすると、痛くて嫌になっちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
素手で扱うと手を切る可能性があるので、必ず手袋を着用してください。
また、屋外で使用する場合は錆びる可能性があるので、防水処理を忘れずに。
「でも、見た目が悪くならない?」という心配も出てくるでしょう。
確かにその通りです。
でも、外側を塗料や板で覆えば、見た目の問題は解決できます。
むしろ、壁の補強になるかもしれませんよ。
この方法は、まるで「壁の鎧作戦」のようですね。
家族で協力して、我が家の防御力アップに取り組むのも楽しいかもしれません。
「今日の任務は北の壁の守備固め!」なんて、冒険気分で盛り上がれそうです。
スチールウールでハクビシン対策をしながら、家族の結束力も高まる。
一石二鳥どころか三鳥くらいありそうですね。
ただし、古い家屋では壁の構造に注意が必要です。
様子を見ながら慎重に作業を進めましょう。
これで、壁の隙間からのハクビシン侵入の心配がぐっと減るはずです。
家族みんなで力を合わせて、安心できる城壁のような家を作り上げましょう。
意外な効果「アルミホイルの樋巻き」で侵入防止
樋を使ったハクビシンの侵入を防ぐ意外な裏技として、アルミホイルの活用が効果的です。「えっ、アルミホイル?お弁当包むやつ?」と思った方、その通りです!
実は、これがハクビシン対策に大活躍するんです。
アルミホイルを使った侵入防止法の手順を見てみましょう。
- 樋の周りをきれいに掃除する
- アルミホイルを30〜50cm幅に切る
- 樋の周りにアルミホイルをぐるぐる巻きにする
- 上端と下端をテープでしっかり固定する
アルミホイルの表面がツルツルしていて滑りやすいため、ハクビシンが樋を登るのを難しくするんです。
まるで「つるつる棒」ゲームのようですね。
ただし、注意点もあります。
強風で飛ばされないよう、しっかり固定することが大切です。
また、定期的に点検して破れたり剥がれたりしていないか確認しましょう。
「でも、見た目が変じゃない?」という心配も出てくるでしょう。
確かにその通りです。
でも、意外とキラキラして綺麗に見えるかもしれません。
「うちの樋、宇宙船みたい!」なんて、新しい話題になるかも。
この方法は、まるで「ピカピカ作戦」のようですね。
家族で協力して、我が家の樋をキラキラさせるのも楽しいかもしれません。
「今日は南側の樋をピカピカにするぞ!」なんて、わくわくしながら作業できそうです。
アルミホイルでハクビシン対策をしながら、実は家の外観が明るくなるという思わぬ効果も。
一石二鳥ですね。
ただし、樋の素材によっては相性が悪い場合もあるので、少しずつ様子を見ながら進めましょう。
これで、樋を使ったハクビシン侵入の心配が減るはずです。
家族みんなで協力して、ピカピカで安心な家づくりを楽しみましょう。