ビワとハクビシン、被害を防ぐには?【樹上と地面の両方を守る】効果的な対策3つを詳しく紹介

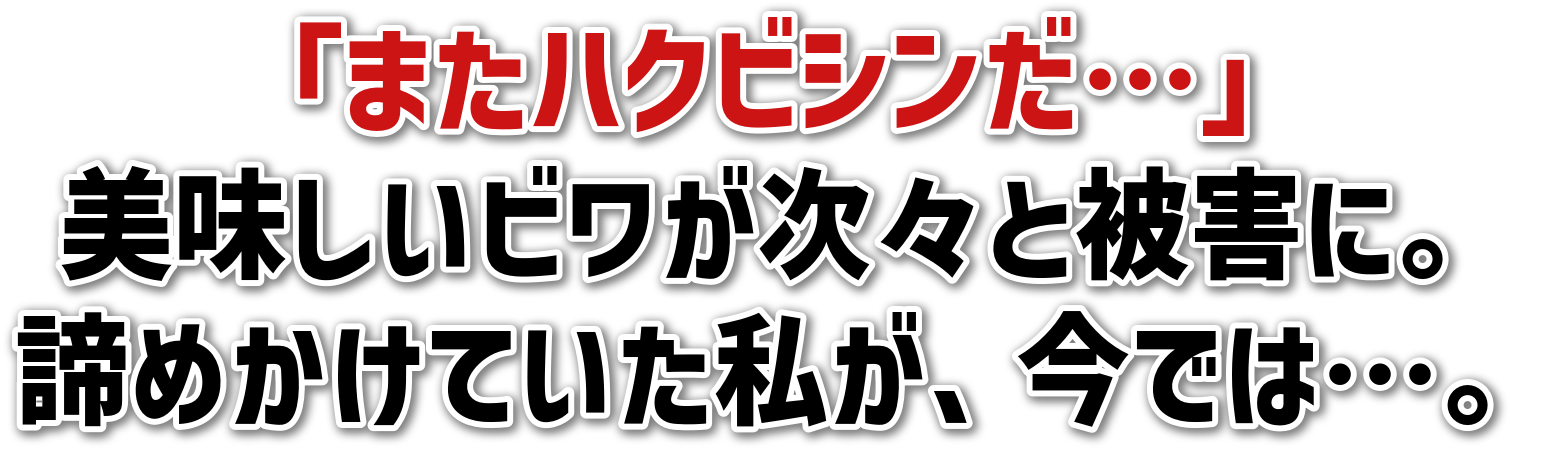
【この記事に書かれてあること】
ビワ栽培者の皆さん、ハクビシンの被害に悩まされていませんか?- ビワの被害が集中する時期と対策のタイミング
- 樹上と地面の両方を守る効果的な防衛策
- ハクビシンの行動パターンを理解して対策に活かす
- 意外と簡単な10の裏技でハクビシンを撃退
- 剪定技術を活用したハクビシン対策と収穫量アップ
実は、ビワを守るには樹上と地面の両方を守ることが重要なんです。
5月上旬から6月中旬がハクビシンの被害ピーク期。
この時期に備えて、効果的な対策を立てましょう。
防鳥ネットや電気柵はもちろん、今回は意外と簡単な10の裏技もご紹介します。
「えっ、そんな方法があったの?」と驚くこと間違いなし。
ビワを守りながら、収穫量アップも狙える方法が盛りだくさん。
さあ、美味しいビワを守るため、一緒にハクビシン対策を学んでいきましょう!
【もくじ】
ビワとハクビシンの被害、深刻な実態と対策

ビワが狙われやすい時期は5月上旬から6月中旬!
ビワの被害は5月上旬から6月中旬がピークです。この時期、ハクビシンの姿を見かけたら要注意!
ビワの実がツヤツヤと色づき始めると、ハクビシンの食欲をそそります。
「あれ?昨日まであんなに立派だったビワが、今朝見たら半分に減ってる…」なんてことになりかねません。
ハクビシンは夜行性のため、昼間は姿を見せません。
でも、夜になると「ガサガサ」「ゴソゴソ」と音を立てながら木に登ってきます。
「まさか、うちの大切なビワが…」と心配になりますよね。
被害を防ぐには、この時期に特に気を付けましょう。
- 木の周りを頻繁に見回る
- 夜間はセンサーライトを設置する
- 熟す前の実は早めに収穫する
「よし、今年こそはハクビシンに負けないぞ!」という気持ちで、大切なビワを守りましょう。
1頭で1晩に10〜15個のビワを食べる「驚異の食欲」
ハクビシンの食欲はすごいんです。なんと1頭で1晩に10〜15個ものビワを平らげてしまいます。
「えっ、そんなに食べるの?」と驚かれるかもしれません。
でも、これが事実なんです。
ハクビシンにとって、ビワは絶好のごちそう。
甘くて栄養満点のビワは、彼らの大好物なんです。
ハクビシンの胃袋は意外と大きく、体重の10%以上の食べ物を一度に食べることができます。
例えば、体重4kgのハクビシンなら、400g以上のビワを一晩で平らげてしまうんです。
この驚異の食欲が、ビワ農家さんを悩ませる原因になっています。
「昨日まであんなにたくさんあったのに…」という嘆きの声をよく聞きます。
ハクビシンの食欲を抑える方法はいくつかあります。
- 防鳥ネットで木全体を覆う
- 熟す前の実は早めに収穫する
- 木の周りに忌避剤を撒く
- 夜間はセンサーライトを点灯させる
「よし、今年こそはハクビシンに負けないぞ!」という気持ちで、大切なビワを守りましょう。
夜間が要注意!日没後2〜3時間が最も活発な時間帯
ハクビシンは夜行性です。特に日没後2〜3時間が最も活発な時間帯なんです。
この時間帯、ビワの木の周りはハクビシンにとって「ごちそう天国」になっちゃいます。
「でも、夜中に見回りなんてできないよ…」と思われるかもしれません。
大丈夫です。
夜間の対策はいくつかあります。
まず、センサーライトの設置がおすすめ。
ハクビシンは明るい光が苦手です。
突然のライトアップに「びっくりぎょうてん」。
木から落ちそうになるほど驚いて逃げ出します。
次に、ラジオを活用する方法も。
夜間放送を流しておくと、人の気配を感じて近づかなくなります。
「カチカチ」という音を出す装置も効果的です。
- センサーライトを設置する
- ラジオの夜間放送を流す
- カチカチ音を出す装置を使う
- 防鳥ネットで木全体を覆う
「よし、今夜からハクビシン対策だ!」という気持ちで、大切なビワを守りましょう。
薬剤散布はかえって「生態系を乱す」逆効果に!
ビワの木に薬剤を散布するのは、実は逆効果なんです。生態系を乱してしまう危険性があるからです。
「えっ、でも薬剤を使えば簡単に追い払えるんじゃないの?」と思われるかもしれません。
確かに一時的にはハクビシンを遠ざけられるかもしれません。
でも、それは長続きしません。
薬剤散布には大きな問題があります。
まず、ビワの実に残留する可能性があります。
これは人間の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
「せっかくのおいしいビワが台無しじゃないか」というわけです。
さらに、薬剤はハクビシンの天敵となる生き物まで駆除してしまう可能性があります。
例えば、フクロウやタヌキなどです。
これらの動物がいなくなると、かえってハクビシンが増えてしまうかもしれません。
では、どうすればいいのでしょうか?
自然な方法でハクビシンを寄せ付けないようにするのが一番です。
- ラベンダーなどの香りの強い植物を植える
- 木酢液を薄めて散布する
- 唐辛子スプレーを使用する
- 木の周りに使用済みの猫砂を撒く
「自然と共存しながらビワを守る」という姿勢が大切なんです。
捕獲して遠くに放すのは「法律違反」の可能性も
ハクビシンを捕まえて遠くに放すのは、実は法律違反になる可能性があるんです。「えっ、そんなの知らなかった!」と驚く人も多いはず。
確かに、「捕まえて遠くに放せば問題解決!」と考えたくなりますよね。
でも、それは大きな間違いです。
なぜなら、ハクビシンは「特定外来生物」に指定されているからです。
特定外来生物は、「捕獲」「運搬」「放出」が法律で禁止されています。
違反すると罰金や懲役の対象になることも。
「善意でやったのに…」と後悔しても遅いんです。
では、どうすればいいのでしょうか?
正しい対処法はいくつかあります。
- 市役所や町役場の担当部署に相談する
- 専門業者に依頼する(ただし費用がかかります)
- 防鳥ネットなどで物理的に侵入を防ぐ
- 忌避剤や音で寄せ付けないようにする
「法律を守りつつ、大切なビワを守る」という姿勢が大切なんです。
ハクビシン対策は根気が必要です。
でも、諦めずに続けることが大切。
「よし、今年こそはハクビシンに負けないぞ!」という気持ちで、大切なビワを守りましょう。
樹上と地面、両面からの効果的な対策法
樹上対策は「防鳥ネット」が最強!設置方法と注意点
防鳥ネットは、ビワの樹上対策の王様です。しっかり設置すれば、ハクビシンの侵入を防ぐ強力な味方になります。
「でも、ネットを張るのって難しそう…」そう思った方も大丈夫!
コツさえつかめば誰でもできるんです。
まず、ネットの目合いは2cm以下のものを選びましょう。
ハクビシンは意外と小さな隙間から侵入できるので、細かい目のネットが必要なんです。
次に、設置方法のポイントをご紹介します。
- ネットは木全体を覆うように
- 地面まで届くくらい長めに
- 支柱を立てて、ネットが木に触れないように
- 隙間ができないよう、しっかり固定
ハクビシンが諦めて帰っていく音なんです。
注意点もあります。
鳥や昆虫が絡まる可能性があるので、こまめに見回りましょう。
「あれ?何か引っかかってる?」と思ったら、すぐに確認です。
防鳥ネットは手間はかかりますが、効果は抜群。
「よし、今年こそハクビシンに勝つぞ!」という気持ちで、しっかり設置しましょう。
地面対策の決め手は「電気柵」!正しい設置で効果アップ
地面からのハクビシン対策なら、電気柵が強い味方です。正しく設置すれば、ビワの木への接近を防げます。
「電気柵って難しそう…」そう思った方、ご安心を。
基本を押さえれば、誰でも設置できるんです。
まず、電気柵の高さは重要です。
地面から20cmと40cmの2段設置が効果的。
ハクビシンの体格に合わせているんです。
次に、設置のコツをご紹介します。
- 柵の周りの草は刈り取る
- 電線は張りすぎず、たるませる
- コーナー部分はしっかり固定
- 定期的に電圧チェック
でも心配いりません。
ハクビシンを傷つけるほどの電圧ではないんです。
注意点もあります。
感電の危険があるので、人が触れないよう注意書きを立てましょう。
「あれ?柵が光ってる?」なんて好奇心は禁物です。
電気柵は設置に少し手間がかかりますが、効果は絶大。
「よし、これでハクビシンとおさらばだ!」という気持ちで、しっかり管理しましょう。
防鳥ネットvs電気柵!どっちがより効果的?
防鳥ネットと電気柵、どちらがより効果的でしょうか?結論から言うと、両方使うのがベストです。
「えっ、両方?費用がかかりすぎじゃ…」そう思った方も多いはず。
でも、両方の良いところを組み合わせると、最強の防御になるんです。
防鳥ネットは樹上からの侵入を防ぎ、電気柵は地面からの接近を阻止します。
いわば、空からと地上からの二段構えの守りなんです。
それぞれの特徴を比べてみましょう。
- 防鳥ネット:設置が少し面倒、でも一度つければ長期間有効
- 電気柵:設置は比較的簡単、でも電源管理や草刈りが必要
ハクビシンが諦めて帰っていく音なんです。
両方使う場合の注意点もあります。
ネットと柵の間に適度な距離を取り、ハクビシンが侵入できそうな隙間を作らないことが大切です。
防鳥ネットと電気柵、両方使えば鉄壁の守り。
「これで今年のビワは安泰だ!」という自信が持てるはずです。
費用はかかりますが、美味しいビワを守る価値は十分にあります。
落下果実の放置は「ハクビシン天国」に!即時回収を
落下したビワをそのままにしていませんか?それ、ハクビシンを呼んでいるようなものです。
即時回収が大切なんです。
「えっ、落ちたビワくらいいいじゃない」そう思った方も多いはず。
でも、これが大きな間違いなんです。
落下果実は、ハクビシンにとって格好の餌。
「美味しそうな匂いがする」とハクビシンが寄ってきて、そのまま木に登って被害が拡大…なんてことも。
落下果実の回収、どうすればいいでしょうか?
- 毎日、決まった時間に見回る
- 落下果実専用のバケツを用意
- 腐った果実も必ず回収
- 回収した果実は堆肥にするのもあり
ビワが落ちた合図かもしれません。
注意点もあります。
回収時は軍手を着用し、虫さされや傷に気をつけましょう。
「痒い!」「痛い!」なんてことにならないよう気をつけて。
落下果実の回収、面倒くさいかもしれません。
でも、これがハクビシン対策の基本中の基本。
「よし、今日も一つも見逃さないぞ!」という気持ちで、しっかり回収しましょう。
剪定で「樹高を低く」!ハクビシン対策と収穫量アップ
剪定でビワの木を低くすれば、ハクビシン対策になるだけでなく、収穫量もアップするんです。一石二鳥の効果があるんですよ。
「えっ、木を低くして大丈夫なの?」そう思う方も多いはず。
でも、適切な剪定は木にとっても良いことなんです。
まず、樹高を3メートル程度に抑えることで、ハクビシンが登りにくくなります。
「ヨイショ」と登ろうとしても、枝が少なくて苦戦するんです。
剪定のポイントをご紹介します。
- 主枝を3〜4本に絞る
- 内向きに伸びる枝は切除
- 日当たりを良くするため、枝の間隔を適度に開ける
- 樹冠の内部まで日光が当たるようにする
これは木が喜んでいる音かもしれませんね。
注意点もあります。
強すぎる剪定は逆効果。
徐々に理想の形に近づけていきましょう。
「あれ?切りすぎちゃった?」なんてことにならないよう、慎重に。
剪定は少し技術が必要ですが、効果は絶大。
「よし、今年は剪定でハクビシン対策と豊作を両立させるぞ!」という気持ちで、丁寧に作業しましょう。
意外と簡単!ハクビシンを寄せ付けない5つの裏技

ラベンダーの植栽で「天然の忌避剤」効果を発揮
ラベンダーを植えるだけで、ハクビシンを寄せ付けない天然の忌避剤になるんです。意外と簡単でしょう?
「えっ、本当に効くの?」と思われるかもしれません。
でも、ハクビシンは強い香りが苦手なんです。
ラベンダーの香りは人間には心地よいですが、ハクビシンにとっては「うわっ、くさい!」という感じなんです。
ラベンダーをビワの木の周りに植えましょう。
根元から1メートルほど離して、円形に植えるのがおすすめです。
「ふわっ」と漂う香りがハクビシンを遠ざけてくれます。
ラベンダーの植え方のコツをご紹介します。
- 日当たりのよい場所を選ぶ
- 水はけの良い土を使う
- 株間は30〜40cm程度空ける
- 定期的に剪定して形を整える
ただし、注意点もあります。
ラベンダーは乾燥に強いですが、水やりは忘れずに。
「あれ?葉っぱがしおれてる?」と気づいたら要注意です。
ラベンダーの植栽、美しさと機能性を兼ね備えた一石二鳥の対策。
「よし、今年はラベンダーでハクビシンを撃退だ!」という気持ちで、さっそく始めてみましょう。
アルミホイルの反射光で「ハクビシンを撃退」!
アルミホイルの反射光でハクビシンを撃退できるんです。これ、意外と効果的なんですよ。
「え?アルミホイルで?」と驚かれるかもしれません。
でも、ハクビシンは光に敏感。
突然の光の反射に「びっくりぎょうてん」してしまうんです。
使い方は簡単。
ビワの枝にアルミホイルを巻き付けるだけ。
風で「カサカサ」と音を立てるのも、ハクビシンを怖がらせる効果があります。
具体的な方法をご紹介しましょう。
- 30cm四方のアルミホイルを用意
- ホイルの中心に小さな穴を開ける
- 穴に枝を通してホイルを固定
- 枝の先端や果実の近くに重点的に取り付ける
- 数日おきに位置を変えると効果アップ
ただし、注意点もあります。
強風の日はホイルが飛ばされる可能性も。
「あれ?ホイルがなくなってる?」と気づいたら、すぐに付け直しましょう。
アルミホイル作戦、お手軽で経済的な対策法です。
「よし、今夜はピカピカ大作戦だ!」という気持ちで、さっそく試してみましょう。
使用済み猫砂で「天敵の匂い」を演出!散布のコツ
使用済みの猫砂を撒くと、ハクビシンを寄せ付けない効果があるんです。意外でしょう?
「えっ、猫砂?」と思われるかもしれません。
でも、これには理由があるんです。
ハクビシンにとって、猫は天敵の一種。
その匂いを嗅ぐだけで「ヒェー、猫がいる!」と逃げ出すんです。
使い方は簡単。
ビワの木の周りに使用済みの猫砂を薄く撒くだけ。
でも、ちょっとしたコツがあります。
- 木の根元から1メートル程度の範囲に撒く
- 厚く撒きすぎず、薄く広く撒く
- 雨が降ったら再度撒き直す
- 2〜3日おきに新しい猫砂に交換する
- 近所の猫カフェに使用済み猫砂をもらいに行くのもアリ
ただし、注意点もあります。
猫砂の匂いが強すぎると、逆に野良猫を引き寄せてしまう可能性も。
「あれ?猫が集まってきた?」なんてことにならないよう、適量を守りましょう。
使用済み猫砂作戦、ちょっと変わった方法ですが、効果は抜群。
「よし、今年は猫の力を借りてハクビシンを撃退だ!」という気持ちで、さっそく試してみましょう。
ペットボトル風車で「不気味な音」を立てて威嚇
ペットボトルで手作り風車を作ると、ハクビシンを威嚇する不気味な音が出せるんです。これ、意外と効果的なんですよ。
「えっ、ペットボトルで?」と思われるかもしれません。
でも、風で回る風車が「カラカラ」という音を立てると、ハクビシンは「なんだこの音!?」と警戒するんです。
作り方は簡単。
ペットボトルを半分に切って、羽根を作るだけ。
具体的な手順をご紹介しましょう。
- 2リットルのペットボトルを用意
- ボトルの真ん中で切る
- 下半分に縦方向の切れ目を入れて羽根を作る
- 中心に穴を開けて、竹串や針金で固定
- ビワの木の枝に取り付ける
ただし、注意点もあります。
強風の日は音が大きくなりすぎる可能性も。
「うるさくて眠れない!」なんて苦情が来ないよう、設置場所には気を付けましょう。
ペットボトル風車作戦、手作りの楽しさとエコな対策を兼ね備えています。
「よし、今日は風車作りに挑戦だ!」という気持ちで、さっそく始めてみましょう。
果実にホットソース塗布!「辛さで学習効果」を狙う
ビワの実にホットソースを薄く塗ると、ハクビシンを寄せ付けなくなるんです。意外な方法ですが、効果は抜群ですよ。
「えっ、ホットソース?食べられなくなるんじゃ…」と心配される方もいるかもしれません。
大丈夫です。
人間が食べる分には水で洗い流せば問題ありません。
ハクビシンは一度辛い思いをすると、二度とその場所に近づかなくなるんです。
「痛い!辛い!」という経験が、強力な学習効果を生むんです。
具体的な方法をご紹介しましょう。
- 市販のホットソースを水で5倍に薄める
- スプレーボトルに入れて噴霧する
- 果実の表面に薄くムラなく塗る
- 3日おきに塗り直す
- 雨が降ったらすぐに塗り直す
ただし、注意点もあります。
あまり強烈な辛さのソースを使うと、ビワの実にダメージを与える可能性も。
「あれ?実が変色してる?」と気づいたら、すぐに水で洗い流しましょう。
ホットソース作戦、ちょっと意外な方法ですが、効果は絶大。
「よし、今年は辛さでハクビシンを撃退だ!」という気持ちで、さっそく試してみましょう。