田畑のハクビシン被害、早期発見のコツは?【足跡チェックが重要】迅速な対応方法3つを解説

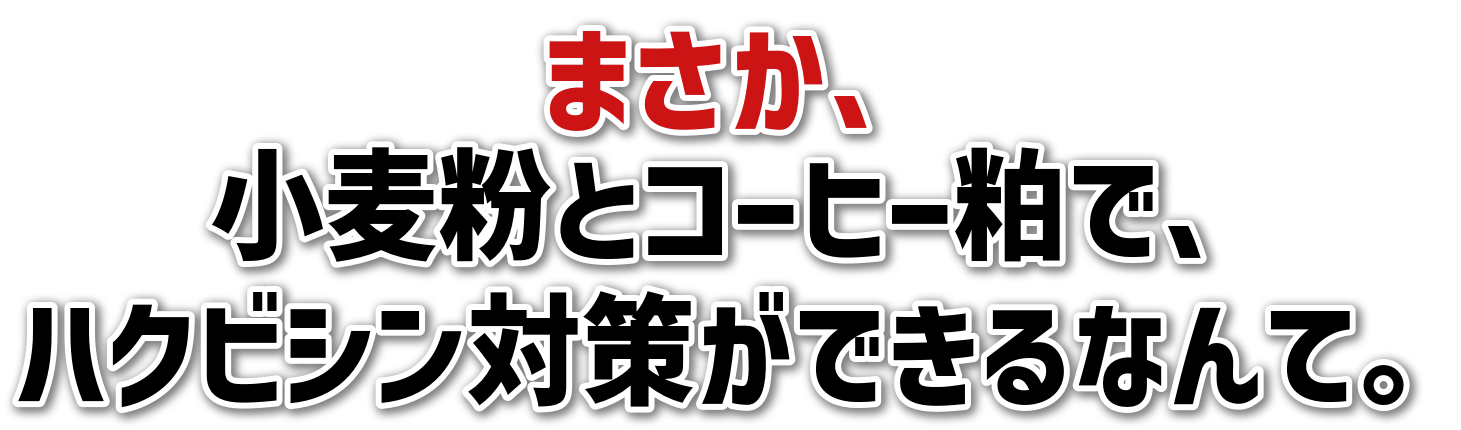
【この記事に書かれてあること】
田畑のハクビシン被害、早期発見が決め手です!- ハクビシンの足跡の特徴を知り、早朝の見回りで被害を早期発見
- 作物の種類別に被害の特徴と発見のコツを把握
- 見落としやすい電線の噛み跡にも注意が必要
- 季節による被害パターンの変化を理解し、効果的な対策を実施
- 5つの驚きの裏技で、プロ級のハクビシン対策を実現
足跡チェックを中心に、効果的な対策方法をご紹介します。
ハクビシンの行動パターンを知り、被害の兆候を見逃さない目を養えば、大切な農作物を守れるんです。
「もう、ハクビシンにやられっぱなしは嫌だ!」そんな思いを抱える皆さん、一緒に対策を学びましょう。
驚くほど簡単で効果的な5つの裏技も伝授します。
これであなたの田畑は鉄壁ガード!
ハクビシンとの知恵比べ、さあ始めましょう!
【もくじ】
田畑のハクビシン被害を早期発見!足跡チェックの重要性

ハクビシンの足跡「5本指の特徴」を見逃すな!
ハクビシンの足跡は5本指が特徴的です。この独特な痕跡を見逃さないことが、被害の早期発見につながります。
ハクビシンの足跡は、まるで小さな人間の手のような形をしているんです。
前足は丸みを帯びた5本指で、後ろ足はやや細長い形状をしています。
「これ、誰かの子どもの手形?」なんて思ってしまうかもしれません。
でも、それがハクビシンの足跡だったりするんです。
足跡の大きさは、前足が約3〜4センチ、後ろ足が約4〜5センチほど。
柔らかい土や泥の上にくっきりと残ることが多いので、見つけやすいんです。
足跡を見つけたら、ぜひ以下のポイントをチェックしてみてください。
- 5本指がはっきりと見えるか
- 前足と後ろ足で形が違うか
- 連続した足跡で、移動経路がわかるか
- 足跡の周辺に、作物の食べ残しはないか
- 足跡の新しさ(乾いているか、湿っているか)
「ほら、ここからこう歩いて、あの作物に向かってるぞ!」なんて、探偵気分で追跡してみるのも楽しいかもしれませんね。
足跡発見のコツは、目線を低くして地面をよく観察すること。
朝露で湿った地面は足跡が残りやすいので、早朝の見回りがおすすめです。
ハクビシン探偵になって、田畑を守る第一歩を踏み出しましょう!
夜行性のハクビシン!「早朝の見回り」がカギ
ハクビシンは夜行性の動物です。だからこそ、早朝の見回りが被害発見の決め手になるんです。
真っ暗な夜、ハクビシンたちはこっそり田畑に忍び込んできます。
「みんな寝てる間に、おいしいごちそうをいただこう」なんて考えているのかもしれませんね。
でも、そんなハクビシンの行動を朝一番で察知できれば、被害を最小限に抑えられるんです。
早朝の見回りには、こんなメリットがあります。
- 新鮮な足跡や糞の発見がしやすい
- 露で湿った地面に残る痕跡が鮮明
- 被害にあった作物をすぐに発見できる
- 昼間の暑さを避けられる
- 朝日で全体が見渡しやすい
でも、早起きは三文の徳とも言います。
朝のさわやかな空気を吸いながら、田畑を守る使命に燃えてみませんか?
見回りのときは、懐中電灯やカメラを持参するのがおすすめです。
暗がりでも痕跡を見逃さず、証拠として記録に残せますからね。
また、定規や測定テープがあれば、足跡のサイズも正確に計れます。
朝もやの立ち込める田畑で、ハクビシンの痕跡を探す。
なんだかわくわくしてきませんか?
早朝の見回りは、田畑を守る探偵になった気分で楽しめるんです。
さあ、明日の朝は少し早起きして、ハクビシン対策の第一歩を踏み出しましょう!
被害の兆候「食べ残しと糞」にも要注意
ハクビシンの被害を見逃さないためには、食べ残しと糞にも注目することが大切です。これらの痕跡は、ハクビシンが確実に田畑に侵入した証拠となるんです。
まず、食べ残しについて。
ハクビシンは意外と好き嫌いが激しい食いしん坊なんです。
「これはおいしい!でもこれはちょっと…」なんて、人間の子どものように食べ物を選り好みします。
そのため、半分かじられた果物や野菜がよく見つかります。
食べ残しの特徴は以下の通りです。
- 果物の場合、皮だけ残されていることが多い
- トウモロコシなら、実だけが食べられて芯が残る
- 野菜は、柔らかい部分だけが食べられている
- かじり跡が不規則で、歯形が残っていることも
- 食べ残しの周りに、足跡が残っていることが多い
ハクビシンの糞は、その特徴的な形状から比較的見つけやすいんです。
「え、動物のうんちを観察するの?」なんて思うかもしれませんが、これが重要な手がかりになるんですよ。
ハクビシンの糞の特徴は次のとおりです。
- 円筒形で、直径約2センチ、長さ3〜5センチ程度
- 黒っぽい色をしている
- 果実の種が混じっていることが多い
- 独特の臭いがする
- 畑の端や、少し離れた場所に見つかることが多い
時間が経つと風化したり、他の動物に踏み荒らされたりする可能性があるからです。
食べ残しと糞、この2つの痕跡を見逃さないことで、ハクビシンの行動パターンがより明確になります。
まるで名探偵のように、証拠を集めて犯人(ハクビシン)の動きを追跡しましょう。
そうすれば、より効果的な対策が立てられるはずです。
見落としがちな「電線の噛み跡」を確認
ハクビシンの被害というと、作物への被害ばかりに目が行きがちです。でも、実は電線の噛み跡も重要な被害の兆候なんです。
この見落としがちな痕跡を確認することで、被害の全容がより明確になります。
ハクビシンは器用な動物で、木を登ったり電線を渡り歩いたりするのが得意です。
「まるでサーカスの綱渡り芸人みたい!」なんて思うかもしれません。
でも、この特技が電線被害につながってしまうんです。
電線の噛み跡には、こんな特徴があります。
- 被覆が不規則にはがされている
- 噛み跡が点々と連続している
- 電線の接続部分に集中していることが多い
- 屋根に近い部分や、樹木の近くに見られやすい
- 被害が進むと、電線が切断されていることも
実は、ハクビシンにとって電線を噛むことは、歯の成長を促す効果があるんです。
人間で言えば、歯ぎしりをするようなものかもしれません。
電線の噛み跡を見つけたら、すぐに対処することが大切です。
放置すると、漏電や停電の原因になる可能性があるからです。
見つけたら、以下の手順で対応しましょう。
- 被害箇所の写真を撮影する
- 電力会社に連絡して、修理を依頼する
- 近隣住民にも注意を呼びかける
- 電線周辺の樹木を剪定し、アクセスを難しくする
- 忌避剤を設置して、再被害を防ぐ
「ああ、こうやって屋根に登ってるんだな」なんて、ハクビシンの動きが手に取るようにわかるかもしれません。
電線をチェックするときは、必ず地上から双眼鏡などを使って安全に確認してくださいね。
危険ですので、絶対に自分で電線に登ったりしないでください。
安全第一で、ハクビシン探偵活動を楽しみましょう!
ハクビシン対策の落とし穴「餌付け」はNG!
ハクビシン対策を頑張っているのに、知らず知らずのうちに「餌付け」をしてしまっていることがあります。これは、対策の大きな落とし穴なんです。
餌付けは絶対にNGです!
「え?私、ハクビシンに餌をあげてないよ?」と思うかもしれません。
でも、実は意図せず餌付けをしてしまっていることがあるんです。
例えば、こんなことはしていませんか?
- 収穫し忘れた果実を放置している
- 生ゴミを屋外に置いている
- ペットのエサを外に置きっぱなしにしている
- コンポストを適切に管理していない
- 落果を拾わずに放置している
「まいどあり!」とばかりに、ハクビシンが何度も訪れるようになってしまいます。
餌付けの問題点は、次のようなことです。
- ハクビシンが人の生活圏に慣れてしまう
- 繰り返し田畑に侵入するようになる
- ハクビシンの個体数が増える可能性がある
- 他の野生動物も集まってくる
- 病気が蔓延するリスクが高まる
それは一時的な同情心であって、長期的には害になるんです。
餌付けを防ぐには、こんな対策をしてみましょう。
- 収穫はこまめに行い、熟れすぎた果実は速やかに処分する
- 生ゴミは密閉容器に入れ、屋内で保管する
- ペットのエサは食べ終わったらすぐに片付ける
- コンポストは蓋付きの容器を使い、適切に管理する
- 落果は毎日拾い集め、適切に処分する
そうすれば、自然と足が遠のいていくはずです。
ハクビシン対策は、彼らと賢く付き合っていくことなんです。
餌付けという落とし穴に気をつけて、上手にハクビシンと距離を保ちましょう。
そうすれば、田畑も守れて、ハクビシンも自然の中で暮らせる、win-winの関係が築けるはずです。
ハクビシン被害の早期発見!作物別の特徴と対策
果樹vs野菜!被害発見の難易度の違い
果樹の方が野菜よりもハクビシン被害を発見しやすいんです。その理由と対策方法を見ていきましょう。
果樹は高い位置に実がなるため、ハクビシンの被害痕がくっきり目立つんです。
「あれ?リンゴにかじり跡が!」なんて感じで、一目で被害に気づきやすいわけです。
一方、野菜は地面に近いところにあるので、被害を見つけるのに少し手間がかかります。
果樹の被害の特徴はこんな感じです。
- 果実に大きなかじり跡がある
- 枝が折れている
- 樹皮に引っかき傷がある
- 地面に半分食べられた果実が落ちている
- 木の周りに足跡が残っている
- 葉っぱがむしられている
- 実に小さな歯型がついている
- 茎が折れている
- 地面に這う野菜が引きずられた跡がある
- 作物の周りの土が荒らされている
野菜の場合は、ネットで覆ったり、忌避剤を散布したりするのがおすすめです。
「えっ、毎日チェックするの大変そう…」なんて思うかもしれません。
でも、朝の散歩がてら見回るだけでも十分なんです。
被害を早期に発見できれば、対策も素早く打てます。
そうすれば、せっかく育てた作物を無駄にせずに済むんです。
果樹と野菜、それぞれの特徴を押さえて、毎日の見回りを習慣にしましょう。
きっと、ハクビシン対策の達人になれますよ!
背の高い作物と低い作物!見回りのポイント
背の高い作物と低い作物では、ハクビシン被害の見つけ方が全然違うんです。それぞれの特徴を知って、効率的な見回りをしましょう。
まず、背の高い作物の代表格といえば、トウモロコシですよね。
トウモロコシのような背の高い作物は、一見すると被害が分かりにくいんです。
「だって、上の方まで見えないもん」なんて思いますよね。
でも、こんなポイントに注目すれば被害を見つけやすくなります。
- 茎の下の方に引っかき傷がないか
- 葉っぱが不自然に折れ曲がっていないか
- 実が落ちていないか
- 茎の根元に足跡が残っていないか
- 周囲の地面が荒らされていないか
キュウリやナスなど、背の低い野菜は全体が見渡せるので、被害を見つけやすそうに思えます。
でも、油断は禁物です。
こんなところをチェックしましょう。
- 葉っぱにかじり跡がないか
- 実が地面に落ちていないか
- 茎が折れていないか
- 地面に引きずった跡がないか
- 作物の周りに糞が落ちていないか
根元から順番に上を見ていけば、見落としが少なくなります。
低い作物は「全体を見渡す」のがポイント。
少し離れた場所から全体を観察すると、不自然な部分が見つけやすくなりますよ。
「でも、毎日そんなに丁寧にチェックするの、時間がかかりそう…」なんて思っちゃいますよね。
大丈夫です。
慣れてくれば、ささっと10分程度で見回りができるようになります。
朝のコーヒータイムついでに、畑をぐるっと一周。
そんな感じで日課にしてみてはいかがでしょうか。
背の高い作物も低い作物も、それぞれの特徴を押さえて見回りをすれば、ハクビシン被害を早期に発見できます。
被害を最小限に抑えて、豊かな収穫を目指しましょう!
根菜類vs果菜類!被害の特徴と発見のコツ
根菜類と果菜類では、ハクビシンの被害パターンが全然違うんです。それぞれの特徴を知って、的確な対策を立てましょう。
まず、根菜類の被害は見つけにくいんです。
だって、地面の下に隠れているんですからね。
「え?じゃあ被害に気づくのは収穫の時?」なんて心配になるかもしれません。
でも、大丈夫。
こんな兆候に注目すれば、早めに被害を発見できます。
- 葉っぱが急に元気をなくしてしまった
- 地面が荒らされている
- 根元の周りに掘った跡がある
- 葉っぱの付け根に噛み跡がある
- 作物の周りに小さな穴が開いている
実が地面から離れた位置にあるので、ハクビシンの痕跡がはっきり残るんですね。
果菜類の被害は、こんな特徴があります。
- 実に大きなかじり跡がある
- 枝が折れている
- 葉っぱが無造作に引きちぎられている
- 半分食べられた実が地面に落ちている
- 茎に引っかき傷がある
地面が荒らされていたり、葉っぱの様子がおかしかったりしたら要注意。
一方、果菜類は「実と枝をチェック」するのがポイントです。
かじり跡や折れた枝を見つけたら、すぐに対策を講じましょう。
「毎日そんなにじっくり見るの、面倒くさそう…」って思いますよね。
でも、コツをつかめば案外簡単なんです。
例えば、水やりのついでに葉っぱの様子をチェック。
収穫作業の合間に地面の状態を確認。
そんな感じで、日常作業に組み込んでしまえば負担も少なくなります。
根菜類と果菜類、それぞれの特徴を理解して、効率的な見回りを心がけましょう。
被害の早期発見が、美味しい野菜づくりの第一歩なんです!
季節による被害パターンの変化に注目
ハクビシンの被害パターンは、季節によってがらりと変わるんです。この変化を理解すれば、より効果的な対策が打てますよ。
春から夏にかけては、新芽や若葉が狙われやすくなります。
「せっかく芽吹いたのに…」なんてガッカリしないように、こんなポイントに注意しましょう。
- 新芽や若葉のかじり跡
- 苗の引き抜き被害
- 果樹の花や若い実のむしり取り
- 野菜の茎の食害
- 畑全体の踏み荒らし
果実や野菜が たわ わに実る時期ですが、ハクビシンにとっても 御馳走 の季節なんです。
こんな被害に要注意です。
- 熟した果実の食害
- 収穫直前の野菜の被害
- 落果の食べ荒らし
- 木の枝の折れ
- 貯蔵庫への侵入痕
例えば、春には新芽を保護するネットを張る。
秋には果実の早めの収穫を心がける。
そんな風に、季節に合わせた対策を講じるのがコツです。
「えー、季節ごとに対策を変えるの?面倒くさそう…」なんて思うかもしれません。
でも、カレンダーに対策のメモを書き込んでおけば、忘れずに済みますよ。
例えば、「3月:新芽保護ネット設置」「9月:果実の早期収穫開始」といった具合です。
季節の変化とともに、ハクビシンの行動も変わります。
その変化に合わせて対策を練ることで、一年を通じて被害を最小限に抑えられるんです。
自然のリズムに寄り添いながら、賢くハクビシン対策をしていきましょう!
作物の種類別「被害の初期症状」チェックリスト
作物によって、ハクビシン被害の初期症状は全然違うんです。種類別のチェックリストを覚えて、被害を早期発見しましょう。
まずは果樹。
果樹の被害は見つけやすいようで意外と見逃しがち。
こんな初期症状に注目です。
- 葉っぱの付け根に小さなかじり跡
- 若い枝の先端が折れている
- 樹皮に細かい引っかき傷
- 花や若い実の数が急に減った
- 木の周りの地面が少し荒らされている
地面に近いので被害が見えにくいこともありますが、こんな症状を見逃さないようにしましょう。
- 葉の縁に不規則な欠け
- 茎の根元に噛み跡
- 実の表面にうっすらとした引っかき傷
- 苗が斜めに傾いている
- 畝の間に小さな足跡
地中にある根が狙われるので、地上部の変化を見逃さないでください。
- 葉っぱが元気なのに、成長が止まった
- 根元の土が盛り上がっている
- 葉っぱの色が急に悪くなった
- 地面にポツポツと小さな穴
- 葉っぱの付け根がわずかに浮いている
でも、毎日の水やりや草取りのついでに、ちょっと注意深く見るだけでOK。
慣れてくれば、ほんの数分で異変に気づけるようになりますよ。
このチェックリストを頭に入れておけば、ハクビシン被害の初期段階で気づくことができます。
早期発見・早期対策で、大切に育てた作物を守りましょう。
「よーし、今日も畑のパトロールだ!」そんな気持ちで、毎日の見回りを楽しんでくださいね。
プロ級のハクビシン被害対策!5つの驚きの裏技
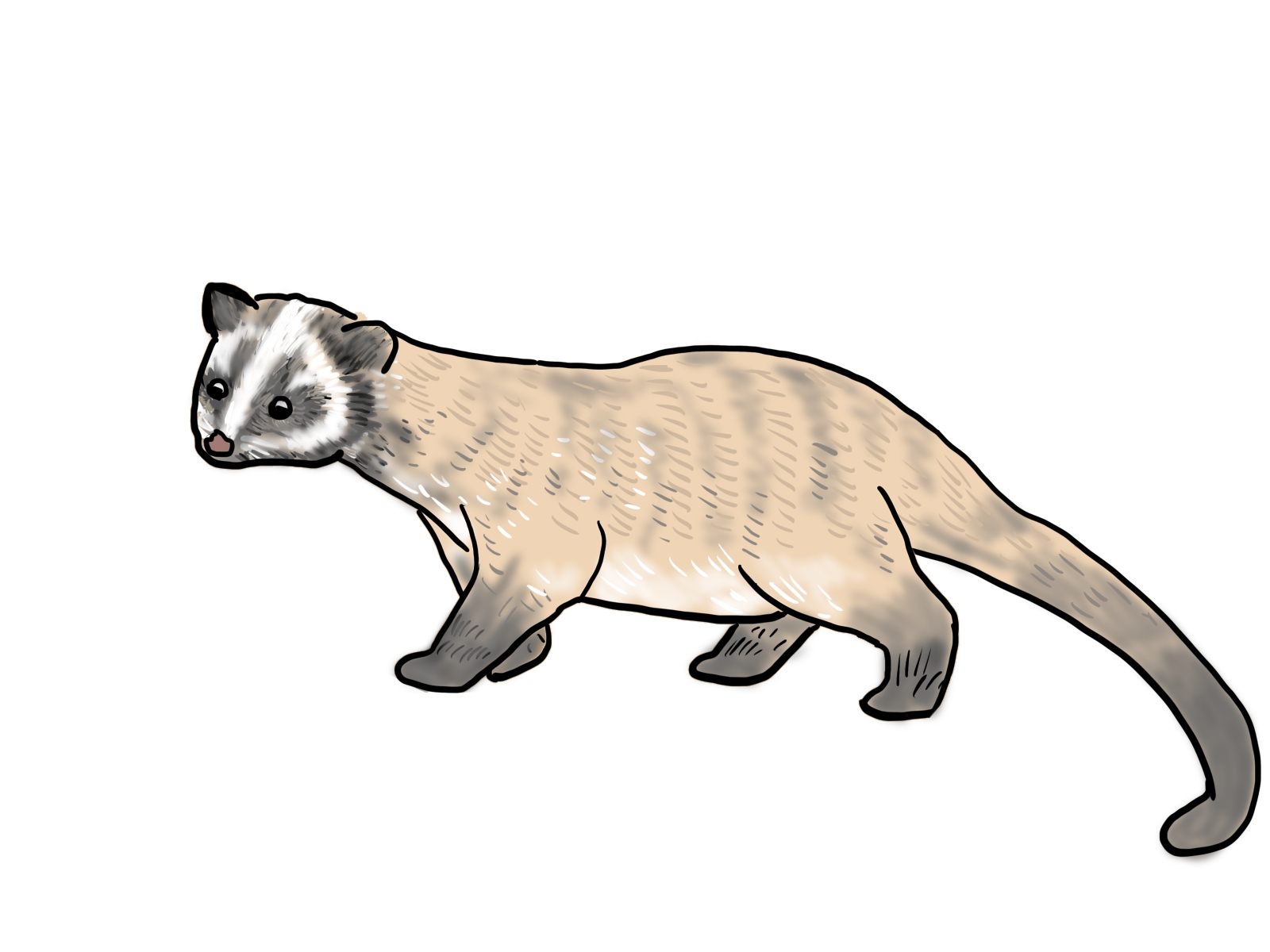
足跡発見に「小麦粉」活用!侵入経路が一目瞭然
小麦粉を使えば、ハクビシンの足跡がくっきり!侵入経路の特定に役立ちます。
ハクビシン対策で悩んでいる皆さん、台所にある小麦粉が強い味方になるんです。
「え?小麦粉?」って思いましたよね。
でも、これがびっくりするほど効果的なんです。
やり方はとっても簡単。
ハクビシンが通りそうな場所に、小麦粉を薄く撒くだけ。
夜の間にハクビシンが通ると、その足跡がくっきりと残るんです。
まるで雪の上に足跡が付いたみたいに、はっきりと見えるんですよ。
この方法のすごいところは、こんなポイントです。
- 足跡の形がはっきり分かる
- 移動経路が一目で分かる
- 複数のハクビシンがいるかどうかも判断できる
- 費用がほとんどかからない
- 環境にやさしい方法
そんな時は、軒下や屋根のある場所を選んで撒くといいですよ。
翌朝、足跡を見つけたら、すかさずカメラで撮影しましょう。
これで、ハクビシンの行動パターンが分かってきます。
「あ、ここからこう行って、あそこに向かってるんだ!」なんて、探偵気分も味わえちゃいます。
ただし、注意点もあります。
小麦粉を撒いた後は、その場所を踏み荒らさないようにしましょう。
人間の足跡で、せっかくのハクビシンの足跡が分からなくなっちゃいますからね。
この方法を使えば、ハクビシンの侵入経路がはっきり分かります。
対策を立てる上で、とっても役立つ情報になりますよ。
さあ、今夜からさっそく小麦粉探偵になってみましょう!
コーヒー粕でハクビシン撃退!驚きの効果
コーヒー粕がハクビシン撃退に効果的!強い香りで寄せ付けません。
コーヒーが好きな方、朝のコーヒータイムがハクビシン対策につながるんです。
「え?コーヒーがハクビシン対策に?」って驚いたでしょ。
実は、使い終わったコーヒー粕が強力な武器になるんです。
ハクビシンは鼻がとっても敏感。
コーヒーの強い香りが、彼らを寄せ付けないんです。
やり方は本当に簡単。
使い終わったコーヒー粕を乾かして、田畑の周りにパラパラっと撒くだけ。
この方法のいいところは、こんなポイントです。
- コストがほとんどかからない
- 環境に優しい
- 肥料としても使える
- 長期間効果が続く
- 人間には良い香りで快適
大丈夫です。
週に1〜2回程度で十分効果があります。
雨が降った後は、もう一度撒き直すのがコツですよ。
コーヒー粕を使う時の注意点もあります。
乾かしてから使うのがポイント。
湿ったままだと、カビが生えやすくなっちゃいます。
また、厚く撒きすぎると土壌が酸性になる可能性があるので、薄く広く撒くのがおすすめです。
「うちはコーヒーを飲まないんだけど…」って方も心配無用。
近所のカフェに相談してみてください。
使い終わったコーヒー粕を分けてもらえるかもしれません。
地域のみんなで協力して、ハクビシン対策をするのも良いアイデアですね。
コーヒー粕で作る香りの結界。
ハクビシンを寄せ付けない、環境にも優しい素敵な対策方法です。
明日の朝からさっそく、コーヒータイムをハクビシン対策タイムに変身させちゃいましょう!
ペットボトルの反射光で警戒心アップ!
ペットボトルの反射光でハクビシンを驚かせる!簡単で効果的な対策方法です。
みなさん、飲み終わったペットボトルを捨てていませんか?
実は、そのペットボトルがハクビシン対策の強い味方になるんです。
「え?ただのゴミじゃないの?」なんて思ったかもしれません。
でも、このペットボトルが意外な力を発揮するんです。
やり方はこうです。
まず、ペットボトルをきれいに洗います。
そして、水を半分くらい入れて、畑の周りに置くんです。
これだけ。
とっても簡単でしょ?
この方法のすごいところは、こんなポイントです。
- お金がほとんどかからない
- 設置が簡単
- 環境に優しい
- 長期間使える
- 見た目もスッキリ
この不規則な光の動きが、ハクビシンを驚かせるんです。
夜行性のハクビシンにとって、突然の光はとっても警戒すべきものなんです。
「でも、ペットボトルを置くだけで本当に効果あるの?」って疑問に思いますよね。
実は、ペットボトルを複数設置することで、さらに効果が上がります。
畑の周りをペットボトルで囲むような感じで置いてみてください。
注意点もあります。
定期的にペットボトルの水を取り替えましょう。
水が汚れたり、藻が生えたりすると反射効果が落ちてしまいます。
また、強風の日はペットボトルが飛ばされないように、少し土に埋めるなどの工夫が必要です。
ペットボトルの反射光で作る、キラキラ防衛線。
簡単で効果的、しかも環境にも優しい素敵な対策方法です。
今日から、飲み終わったペットボトルを宝物に変えちゃいましょう!
ハクビシンびっくりの光の結界の完成です。
古いCDで即席「キラキラ結界」完成!
古いCDで作るキラキラ結界がハクビシンを驚かせます!簡単で効果的な対策方法をご紹介します。
皆さんの家に、使わなくなった古いCDはありませんか?
そのCDが、ハクビシン対策の強力な武器になるんです。
「えっ、あのカラオケで歌った古いCD?」そうなんです。
捨てずにとっておいて正解でしたね。
やり方はとってもシンプル。
古いCDをひもで畑の周りに吊るすだけです。
風に揺られて回転するCDが、光を反射してキラキラ光るんです。
これがハクビシンを驚かせる仕組みなんです。
この方法の素晴らしいところは、こんなポイントです。
- 費用がほとんどかからない
- 設置が簡単
- 見た目がきれい
- 長期間使える
- 音も出るので効果倍増
夜行性の彼らにとって、突然のキラキラは要注意信号。
近づきにくくなるんです。
「でも、CDを1枚吊るすだけじゃ効果ないんじゃない?」って思いましたか?
その通りです。
複数のCDを使うのがコツ。
畑の周りをぐるりと囲むように吊るすと、効果抜群です。
ちょっとした工夫で、さらに効果アップ!
CDの表面に反射テープを貼ると、もっとキラキラ度がアップします。
また、CDとCDの間に風鈴を吊るすと、音も加わってさらに効果的。
ハクビシンびっくりの光と音の結界の完成です。
注意点もあります。
強風の日は、CDが飛ばされないようにしっかり固定しましょう。
また、長期間外に置くと劣化するので、定期的に新しいものと交換するのがおすすめです。
古いCDで作る「キラキラ結界」。
簡単で効果的、しかも見た目もきれいな素敵な対策方法です。
今日から、あなたの畑はディスコ会場に大変身!
ハクビシンは踊りたくなっちゃうかも?
いやいや、逃げ出しちゃうでしょうね。
唐辛子スプレーで「辛い思い出」を植え付ける
唐辛子スプレーでハクビシンに「辛い思い出」を!効果的で安全な対策方法をご紹介します。
皆さん、カレーやキムチなど辛い物は好きですか?
実は、ハクビシンは辛いものが大の苦手なんです。
「へぇ、ハクビシンって辛いもの食べないんだ」そうなんです。
この特徴を利用して、効果的な対策ができるんです。
やり方は簡単。
唐辛子パウダーを水で薄めてスプレーボトルに入れるだけ。
これを作物の周りに吹きかけるんです。
ハクビシンがこの辛い香りを嗅ぐと、「うわっ、ここヤバイ!」って思って近づかなくなるんです。
この方法の良いところは、こんなポイントです。
- 材料が安くて手に入りやすい
- 作り方が簡単
- 人体に害がない
- 環境にも優しい
- 長期間効果が持続する
でも、大丈夫。
動物を傷つけるものではありません。
ただ、「ここは辛くて嫌だな」という記憶を植え付けるだけなんです。
「でも、雨が降ったら効果がなくなっちゃうんじゃない?」って心配になりますよね。
その通りです。
雨が降った後は、再度スプレーをする必要があります。
定期的に吹きかけるのがコツです。
ちょっとした工夫で、さらに効果アップ!
唐辛子パウダーにニンニクパウダーを混ぜると、さらに強力になります。
ハクビシンは強い香りも苦手なので、ダブルパンチになるんです。
注意点もあります。
スプレーを作る時や使う時は、目や鼻に入らないように気をつけましょう。
ゴーグルや手袋を着用するのがおすすめです。
また、風向きに注意して吹きかけてくださいね。
唐辛子スプレーで作る「辛い結界」。
簡単で効果的、しかも安全な素敵な対策方法です。
今日から、あなたの畑は辛いもの好きにはたまらない、でもハクビシンには「お断り」のスパイシーゾーンに変身です!
ハクビシンに「ここはちょっと刺激が強すぎるなぁ」って思わせちゃいましょう。