ハクビシン対策の基本とは?【侵入防止と環境改善がカギ】被害予防と撃退の効果的な方法5つを解説

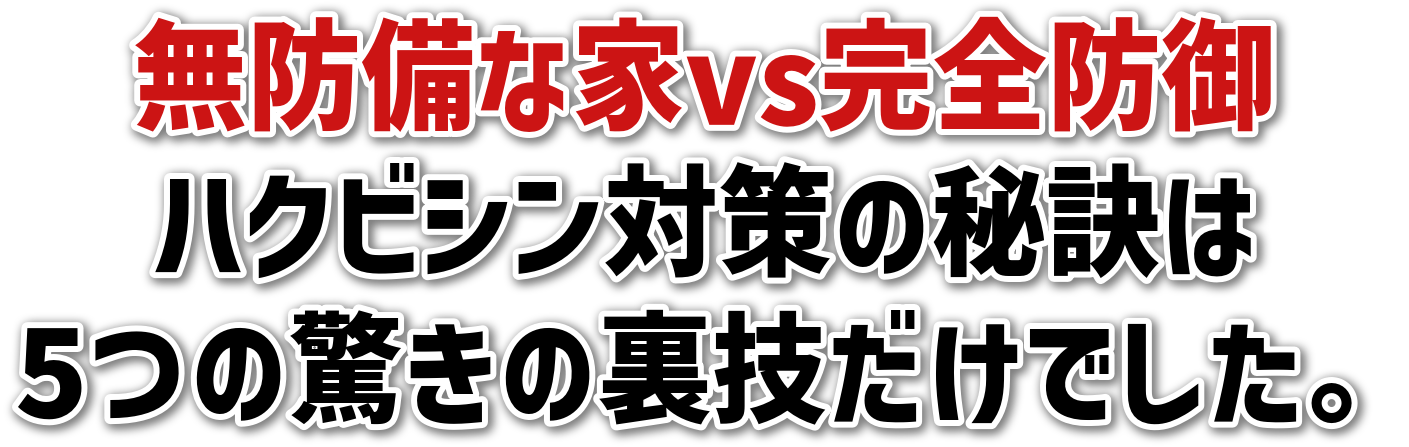
【この記事に書かれてあること】
ハクビシンの被害に悩まされていませんか?- ハクビシン被害の種類と深刻度を理解し、対策の重要性を認識
- 侵入経路の特定と完全封鎖が最も効果的な予防策
- 餌となる果物や生ゴミの適切な管理が被害予防の基本
- 光と音を組み合わせた撃退法や物理的防御の効果を比較
- 身近な材料を使った5つの驚きの裏技で、手軽に対策を実践
屋根裏からの物音、果樹園の荒らし、不気味な足跡…。
これらはすべてハクビシンの仕業かもしれません。
でも、大丈夫。
効果的な対策方法があるんです。
この記事では、ハクビシン対策の基本から驚きの裏技まで、すべてをご紹介します。
侵入防止と環境改善がカギとなる対策の数々で、あなたの家や庭を守りましょう。
「もうハクビシンには困らない!」そんな日々を取り戻すために、一緒に学んでいきましょう。
【もくじ】
ハクビシン対策の基本とは?侵入防止と環境改善がカギ

ハクビシンによる被害の種類と深刻度を知ろう!
ハクビシンの被害は意外と多岐にわたり、深刻な問題を引き起こすことがあります。主な被害は4種類。
屋根裏への侵入、果物や野菜の食害、糞尿による衛生被害、そして騒音被害です。
まず、屋根裏への侵入。
「えっ、うちの天井からガサガサ音がする…」なんて経験ありませんか?
実はこれ、ハクビシンが屋根裏で運動会を開いている証拠かもしれません。
屋根裏に住み着かれると、断熱材を噛み砕いて巣材にされたり、電線をかじられたりして家屋に深刻な被害が出ることも。
次に果物や野菜の食害。
「せっかく育てた野菜が…」と嘆く声が聞こえてきそうです。
ハクビシンは果物や野菜が大好物。
特に熟した果実を狙います。
一晩で収穫を台無しにされることも。
3つ目は糞尿による衛生被害。
「うっ、この臭いは…」というわけで、糞尿の臭いと汚れは深刻な問題です。
しかも、病原体を含む可能性があるので健康被害のリスクも。
最後は騒音被害。
夜中にガタガタ、ドタバタと。
「もう眠れない!」なんて状況に陥ることも。
これらの被害の深刻度は、放置すればするほど高まります。
早期発見・早期対策が極めて重要なんです。
被害の種類を知り、日頃から警戒することが大切です。
「うちは大丈夫」と油断は禁物。
ハクビシン対策、今すぐ始めましょう!
侵入経路を特定し「完全封鎖」が最重要ポイント
ハクビシン対策の要、それは侵入経路の特定と完全封鎖です。「どこから入ってくるの?」と思う人も多いはず。
実は、ハクビシンは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。
まず、侵入経路を知ることが大切。
主な侵入口は以下の通りです。
- 屋根のすき間や破損箇所
- 換気口や排水管
- 壁や床下の隙間
- 樹木や電線からの飛び移り
- 開いた窓やドア
ハクビシンはわずか5cmの隙間があれば侵入可能なんです。
「うちは大丈夫」と思っていても、意外な所に侵入口があるかも。
侵入経路を見つけたら、すぐに封鎖することが重要です。
金網や板で塞ぐのが効果的。
ただし、ハクビシンは歯や爪が強いので、薄い材質だとかじって破壊されることも。
丈夫な材質を選びましょう。
「でも、どうやって見つければいいの?」という声が聞こえてきそうです。
夜間に家の周りを懐中電灯で照らしながら点検するのがおすすめ。
ハクビシンの足跡や毛、糞などの痕跡を探すのも有効です。
侵入経路の封鎖は一度で終わりではありません。
定期的な点検と補修が必要です。
「面倒くさい…」と思うかもしれませんが、これが最も効果的な対策なんです。
侵入を許さない環境づくりこそが、ハクビシン対策の基本中の基本。
完全封鎖で、安心・安全な住まいを守りましょう!
餌となる果物や生ゴミの管理が被害予防の第一歩
ハクビシン対策の第一歩、それは餌の管理です。「え?餌なんてあげてないよ」と思う人も多いはず。
でも、実は知らず知らずのうちに餌場を提供しているかもしれません。
ハクビシンの大好物、それは果物と野菜。
特に熟した果実は格別の味だとか。
庭に果樹があると、それだけでハクビシンを呼び寄せる原因に。
「せっかく育てた果物が…」なんて悲しい思いをしないために、以下の対策が効果的です。
- 果物は早めに収穫する
- 落下した果実はすぐに片付ける
- 果樹にネットを掛ける
- 収穫後の枝の剪定をこまめに行う
「えっ、ゴミまで食べるの?」と驚く声が聞こえてきそう。
ハクビシンは雑食性で、生ゴミも立派な餌になるんです。
以下の点に気をつけましょう。
- 生ゴミは密閉容器に入れる
- ゴミ出しは収集日の朝に行う
- コンポストは蓋付きのものを使用する
- ペットフードは屋外に放置しない
でも、餌がなければハクビシンは寄ってこないんです。
餌の管理は、実は最も効果的で簡単な対策なんです。
餌の管理は一度やって終わりではありません。
継続的な取り組みが大切です。
「面倒くさい…」と思うこともあるでしょう。
でも、これが被害予防の基本。
小さな努力の積み重ねが、大きな効果を生むんです。
さあ、今日から餌の管理を始めましょう!
ハクビシンのいない快適な生活が待っていますよ。
ハクビシン対策を放置すると「最悪の事態」に
ハクビシン対策、「面倒だな」「そのうちやろう」なんて後回しにしていませんか?実は、放置することで最悪の事態を招く可能性があるんです。
どんな事態になるのか、一緒に見ていきましょう。
まず、屋根裏での繁殖。
「えっ、子育てまで?」と驚く声が聞こえてきそうです。
そう、ハクビシンは屋根裏を安全な巣として利用します。
すると何が起こるか。
- 糞尿被害の拡大
- 天井のシミや悪臭の増加
- 建材の腐食による家屋の損傷
- 電線の噛み切りによる火災のリスク
でも、これは氷山の一角。
もっと怖いのは、健康被害です。
ハクビシンの糞尿には、様々な病原体が含まれている可能性があります。
放置すると、以下のようなリスクが高まります。
- 寄生虫感染症
- サルモネラ菌による食中毒
- レプトスピラ症
- アレルギー反応の誘発
特に小さな子どもやお年寄り、ペットがいる家庭では要注意です。
さらに、農作物への被害も深刻です。
一晩で収穫を台無しにされることも。
「せっかくの楽しみが…」と落胆する声が聞こえてきそうです。
対策を放置すると、問題は雪だるま式に大きくなるんです。
小さな兆候を見逃さず、早めの対策が重要。
「今のうちに手を打っておけば…」と後悔する前に、今すぐ行動を起こしましょう。
あなたの大切な家族と家を守るために、ハクビシン対策は待ったなしです!
餌付けはNG!逆効果になる対策に要注意
ハクビシン対策、善意から始めたことが逆効果になることがあるんです。特に注意したいのが「餌付け」。
「かわいそうだから…」なんて思って餌をあげていませんか?
これが大きな間違いなんです。
餌付けの問題点、一緒に見ていきましょう。
- ハクビシンが定着してしまう
- 個体数が増加する
- 被害が拡大する
- 近隣にも迷惑がかかる
そう、餌付けは絶対にNGなんです。
一度餌をもらった場所には、ハクビシンはまた来ようとします。
「ここにはごちそうがある」と覚えてしまうんです。
他にも、やってはいけない対策があります。
例えば、市販の殺鼠剤の使用。
「どうせネズミみたいなものでしょ?」なんて考えていませんか?
実は、これも大きな間違い。
- 法律違反の可能性がある
- 他の動物に悪影響を与える
- 死骸が腐敗して悪臭の原因に
- 生態系のバランスを崩す
そう、善意から始めたことが、思わぬ事態を引き起こすことがあるんです。
では、どうすればいいの?
正しい対策は、ハクビシンを寄せ付けない環境づくり。
餌になるものを管理し、侵入経路を塞ぎ、光や音で追い払う。
これが基本です。
「難しそう…」と思うかもしれません。
でも、一つずつ着実に対策を積み重ねていけば大丈夫。
逆効果な対策に惑わされず、正しい知識を持って取り組みましょう。
あなたの家とハクビシン、どちらも幸せな共存を目指して!
効果的なハクビシン撃退法と長期的な管理のコツ
光と音を組み合わせた撃退vsネット設置による物理的防御
ハクビシン撃退には、光と音を組み合わせた方法と、ネットによる物理的防御の2つが効果的です。どちらを選ぶ?
それぞれの特徴を見てみましょう。
まず、光と音を使った撃退法。
これは、ハクビシンの苦手な刺激を利用するんです。
「ピカッ」と突然の光、「ギャー」という不快な音。
これらがハクビシンを驚かせ、寄せ付けなくするわけです。
- 動体センサー付きライト:動きを感知して点灯
- 超音波発生器:人間には聞こえない高周波音を出す
- ラジオ:人間の声や音楽でハクビシンを怯えさせる
「わー、怖い!」とハクビシンが思うような環境を作るんです。
一方、ネットによる物理的防御。
これは文字通り、ハクビシンの侵入を物理的に阻止する方法です。
- 目の細かい金網:屋根や壁の隙間を塞ぐ
- 防獣ネット:庭や畑を覆う
- 電気柵:軽い電気ショックでハクビシンを学習させる
実は、両方を組み合わせるのが最強なんです。
ネットで物理的に防ぎつつ、光と音で心理的にも撃退。
これで完璧な防御網の出来上がり!
ただし、注意点も。
光と音は周囲への配慮が必要です。
ご近所迷惑にならないよう、音量や光の向きには気をつけましょう。
ネットも、見た目や設置の手間を考慮する必要がありますね。
結局のところ、自宅の環境に合わせて最適な組み合わせを見つけるのがポイント。
「うちの庭にはこれが合いそう!」という感じで、試行錯誤しながら見つけていくのがおすすめです。
ハクビシン対策、頑張りましょう!
忌避剤の使用vs庭の環境整備「どちらが効果的?」
ハクビシン対策、忌避剤を使うか、それとも庭の環境を整備するか。どっちがいいの?
結論から言うと、両方とも大切なんです。
でも、それぞれに特徴があるので、見ていきましょう。
まず、忌避剤。
これはハクビシンの嫌いな匂いを利用して寄せ付けない方法です。
- 市販の忌避剤:専用の薬剤を散布
- 天然の忌避剤:唐辛子や木酢液などを使用
- 匂いの強い植物:ラベンダーやミントを植える
即効性があり、手軽に始められるのが魅力。
一方、庭の環境整備。
これはハクビシンにとって魅力的な環境をなくす方法です。
- 果物や野菜の管理:熟れすぎる前に収穫
- 落ち葉の掃除:隠れ場所をなくす
- ゴミの適切な保管:餌になるものを片付ける
- 水たまりの除去:水場をなくす
効果は徐々に出てきますが、長期的には確実です。
どっちがいいの?
実は、組み合わせるのがベスト。
忌避剤で即効性を出しつつ、環境整備で長期的な効果を狙う。
これが理想的な戦略なんです。
ただし、忌避剤は効果が一時的なので、定期的な再散布が必要。
「面倒くさい…」と思うかもしれません。
環境整備も継続的な手入れが大切。
でも、きれいな庭になるというおまけ付き!
結局のところ、自分の生活スタイルに合わせて、できることから始めるのがコツ。
「よし、まずは庭の掃除から!」なんて感じで。
小さな一歩から、大きな効果が生まれるんです。
がんばりましょう!
予防重視の対策vs撃退中心の対策「コスパの差は歴然」
ハクビシン対策、予防と撃退、どっちを重視する?実は、予防重視の対策の方がコスパ抜群なんです。
なぜそうなのか、見ていきましょう。
まず、予防重視の対策。
これは、ハクビシンが来る前に手を打つ方法です。
- 侵入経路の封鎖:屋根や壁の隙間をふさぐ
- 餌の管理:果物や生ゴミを適切に処理
- 庭の整備:隠れ場所をなくす
- 忌避剤の定期的な使用:寄せ付けない環境作り
初期投資は必要ですが、長期的には経済的。
一方、撃退中心の対策。
これは、ハクビシンが来てから追い払う方法です。
- 光や音による威嚇:センサーライトや超音波装置
- 物理的な追い払い:人が直接追い出す
- 捕獲:捕獲器の設置(ただし、法律に注意)
即効性はありますが、繰り返し必要になることも。
コスパの差はどこにある?
それは、被害の有無なんです。
予防対策なら、被害が起こる前に防げます。
でも撃退中心だと、被害が起きてからの対応。
家の修理費や精神的ストレスを考えると、予防の方がずっとお得なんです。
「えっ、そんなに違うの?」と驚く声が聞こえてきそう。
例えば、屋根裏に住み着かれた場合を想像してみてください。
糞尿被害、悪臭、天井の染み…。
その修理費と手間を考えると、予防対策の費用なんて可愛いものです。
だからこそ、予防に力を入れるのがおすすめ。
「でも、面倒くさそう…」なんて思わないでください。
少しずつでいいんです。
今日からできることから始めましょう。
きっと、将来の自分に感謝されますよ!
季節ごとの対策見直しと継続的な点検が決め手に
ハクビシン対策、一度やったらおしまい?いいえ、季節ごとの見直しと継続的な点検が決め手なんです。
なぜそうなのか、詳しく見ていきましょう。
ハクビシンの行動は季節によって変わります。
例えば、
- 春:繁殖期で活動が活発に
- 夏:果物が豊富で食害のリスクが高まる
- 秋:冬に備えて食べ物を探し回る
- 冬:寒さを避けて屋内に侵入しやすい
だからこそ、季節に合わせた対策が必要なんです。
春なら繁殖期に備えて侵入経路の再確認。
夏は果樹の管理を徹底。
秋は落ち葉の掃除で隠れ場所をなくす。
冬は暖かい屋内への侵入を防ぐ。
こんな感じで、季節ごとに重点を変えていくんです。
でも、それだけじゃありません。
継続的な点検も大切です。
例えば、
- 週1回:庭の見回りと餌になるものの確認
- 月1回:家の周りの侵入経路チェック
- 季節の変わり目:対策全体の見直し
でも、これが効果的なんです。
小さな変化を見逃さず、早めに対応することで、大きな被害を防げるんです。
ポイントは、この点検を習慣にすること。
「面倒くさいなぁ」と思わず、「我が家を守る大切な仕事」と考えてみてください。
家族で分担したり、カレンダーにメモしたりするのもいいですね。
結局のところ、ハクビシン対策は継続が力。
「よし、今日から始めよう!」そんな気持ちで取り組んでみませんか?
きっと、安心して暮らせる家づくりにつながりますよ。
近隣住民との連携で「地域ぐるみ」の対策を
ハクビシン対策、自分の家だけじゃダメ?そうなんです。
近隣住民と連携した地域ぐるみの対策が効果抜群なんです。
なぜそうなのか、詳しく見ていきましょう。
ハクビシンは、1晩で数百メートルも移動します。
つまり、あなたの家だけ対策しても、お隣から侵入されちゃう可能性が。
「ええっ、そんな〜」と思いますよね。
だからこそ、地域全体で取り組むことが大切なんです。
地域ぐるみの対策、具体的にはこんな感じ。
- 情報共有:被害状況や効果的だった対策を共有
- 一斉清掃:餌になる果物や生ゴミを地域で一斉に管理
- 見回り:交代で地域のパトロールを実施
- 勉強会:専門家を呼んで対策方法を学ぶ
これ、実はすごく効果的なんです。
例えば、情報共有。
「うちの庭に来たよ」「〇〇の対策が効いたよ」なんて情報が集まれば、地域全体の対策レベルがグッと上がります。
一斉清掃も、広い範囲でハクビシンの餌を減らせるから効果大。
でも、「ご近所付き合いが苦手…」なんて思う人もいるかも。
大丈夫、最初は挨拶から始めればいいんです。
「ハクビシンの被害、困ってません?」なんて声をかけてみるのも。
意外と同じ悩みを持つ人が見つかるかも。
ポイントは、無理せず楽しく取り組むこと。
例えば、対策を兼ねた地域のバーベキュー大会なんてどう?
果物の収穫祭で、ハクビシンの餌を一掃するのも面白そう。
結局のところ、ハクビシン対策は地域の絆づくりにもつながるんです。
「よし、まずは回覧板で呼びかけてみよう!」そんな小さな一歩から、大きな変化が生まれるかもしれません。
みんなで協力して、ハクビシンフリーの街づくり、始めてみませんか?
驚きの裏技!身近な材料で実践できるハクビシン対策5選

ペットボトルの反射光でハクビシンを威嚇!設置のコツ
ペットボトルを使ったハクビシン対策、意外と効果的なんです。光の反射を利用して、ハクビシンを威嚇する方法です。
まず、なぜペットボトルが効くの?
ハクビシンは光に敏感なんです。
突然のキラキラした光は、彼らにとって「ヒエッ、何か危ないぞ!」という警告サインになるわけ。
では、具体的な設置方法を見ていきましょう。
- 透明なペットボトルを用意する
- 中に水を半分ほど入れる
- 庭やベランダの日当たりのいい場所に置く
- 複数のボトルを不規則に配置する
でも、これが意外と効果的なんです。
ポイントは、設置場所と数。
ハクビシンの侵入経路を予想して、そこを中心に置きましょう。
1本だけじゃなく、3本とか5本とか、複数置くのがコツです。
さらに効果を上げたい場合は、ボトルの中に小さな鈴やアルミホイルの切れ端を入れるのもおすすめ。
風で揺れると「チリンチリン」と音がして、視覚と聴覚の両方でハクビシンを驚かせられます。
ただし、注意点も。
強風の日はボトルが飛ばされる可能性があるので、重しを置くなどの工夫が必要です。
また、長期間放置すると水が汚れて虫の温床になることも。
定期的な水の入れ替えを忘れずに。
「こんな簡単なことで本当に効果あるの?」なんて半信半疑かもしれません。
でも、試してみる価値は十分にあります。
家にあるものでできる手軽な対策、ぜひチャレンジしてみてください!
使用済み猫砂でハクビシンを撃退!効果的な撒き方
使用済みの猫砂でハクビシン対策?「えっ、そんなのでいいの?」って思うかもしれませんね。
でも、これが意外と効果的なんです。
なぜ猫砂が効くのか?
それは、ハクビシンが猫を天敵と認識しているからなんです。
猫の匂いがするところは危険だと感じて、近づかなくなるわけです。
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- 使用済みの猫砂を用意する
- 庭や侵入経路周辺に薄く撒く
- 雨で流れないよう、屋根のある場所も活用
- 1週間ほどで新しいものに交換する
確かに、人間の鼻にも多少匂いますが、それほど強烈ではありません。
むしろ、その匂いがハクビシン対策には重要なんです。
効果を高めるコツは、撒き方と交換のタイミング。
ハクビシンの侵入しそうな場所を中心に、まんべんなく薄く撒きます。
ポイントは「薄く」です。
厚く撒きすぎると、逆効果になる可能性も。
また、猫砂は雨で流れてしまうので、軒下など雨の当たりにくい場所に撒くのもおすすめ。
さらに、効果を持続させるために1週間ごとの交換を忘れずに。
「でも、うちには猫がいないよ」という人も大丈夫。
近所の猫好きさんや動物病院にお願いして、使用済みの猫砂をもらうのも手です。
「ハクビシン対策に使いたいんです」って説明すれば、快く協力してくれる人も多いはず。
身近なもので、しかも費用もほとんどかからない対策。
試してみる価値は十分にありますよ。
さあ、猫砂でハクビシンにバイバイしましょう!
コーヒーかすが強力な「天然の忌避剤」に変身
コーヒーかすでハクビシン対策?「えっ、そんなのでいいの?」って思いますよね。
でも、これが意外と効果的なんです。
コーヒーかすは、強力な天然の忌避剤に変身するんです。
なぜコーヒーかすが効くの?
それは、ハクビシンが苦手とする強い香りのせいなんです。
コーヒーの香りが、ハクビシンの敏感な鼻をくすぐって「ここは危険だぞ」と警告を発するわけです。
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- 使用済みのコーヒーかすを乾燥させる
- 庭や侵入経路周辺に薄く撒く
- 植木鉢や軒下にも置いてみる
- 雨が降ったら新しいものに交換する
そう、家庭から出る廃棄物を有効活用できるのも、この方法の魅力なんです。
効果を高めるコツは、乾燥と配置。
コーヒーかすは湿っていると効果が薄れるので、しっかり乾燥させることが大切。
天日干しでOKです。
そして、ハクビシンの侵入しそうな場所を中心に、まんべんなく撒きます。
さらに、小さな容器に入れて軒下や窓際に置くのもおすすめ。
こうすることで、雨に流されにくくなります。
ただし、カビが生えないよう、定期的な交換は忘れずに。
「でも、うちはコーヒーを飲まないんだけど…」という人も心配無用。
近所のカフェに相談してみるのも手です。
「ハクビシン対策に使いたいんです」って説明すれば、使用済みのコーヒーかすをもらえるかもしれません。
コーヒーかすは植物の肥料としても使えるので、一石二鳥。
庭の手入れをしながらハクビシン対策ができちゃいます。
さあ、コーヒーの香りで、ハクビシンにさよならしましょう!
風鈴の音で警戒心を刺激!効果的な設置場所とは
風鈴でハクビシン対策?「えっ、夏の風物詩があんなことに使えるの?」って驚くかもしれませんね。
でも、これが意外と効果的なんです。
風鈴の音が、ハクビシンの警戒心を刺激するんです。
なぜ風鈴が効くの?
それは、ハクビシンが予期せぬ音に敏感だからなんです。
突然の「チリンチリン」という音が、ハクビシンに「ここは危険かも?」と思わせるわけです。
では、具体的な設置方法を見ていきましょう。
- 金属製の風鈴を選ぶ(音が澄んでいるため)
- ハクビシンの侵入経路に近い場所に設置
- 複数の風鈴を不規則に配置
- 風通しの良い場所を選ぶ
確かに、夜中にジャラジャラ鳴り続けるのは問題ですよね。
でも大丈夫、ちょっとした工夫で解決できます。
効果を高めるコツは、設置場所と音量調整。
ハクビシンの侵入しそうな場所を中心に、複数の風鈴を不規則に配置します。
ただし、あまり大きな音が出ないよう、短冊の長さを調整するのがポイント。
さらに、風通しの良い場所に設置することで、微かな風でも音が鳴るようになります。
軒下や窓際、庭木の枝などが理想的です。
「でも、うちは風鈴を持ってないよ」という人も心配無用。
百均ショップでも手に入りますし、手作りするのも面白いかも。
ペットボトルや空き缶を使って、オリジナルの風鈴を作ってみるのはどうでしょう?
風鈴は見た目も涼しげで、夏の雰囲気を楽しめるのも魅力。
ハクビシン対策をしながら、季節の風情も味わえる一石二鳥の方法です。
さあ、風鈴の音色で、ハクビシンにさよならしましょう!
ガムテープの意外な使い方!侵入経路封鎖の新提案
ガムテープでハクビシン対策?「えっ、そんな身近なもので大丈夫なの?」って思いますよね。
でも、これが意外と効果的なんです。
ガムテープを使って、ハクビシンの侵入経路を封鎖できるんです。
なぜガムテープが効くの?
それは、ハクビシンが粘着物を嫌うからなんです。
体毛が粘着面にくっつくと不快に感じて、その場所を避けるようになるわけです。
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- 幅広のガムテープを用意する
- 侵入経路(隙間や穴)に粘着面を外側にして貼る
- 屋根や壁の端など、よじ登りそうな場所にも貼る
- 定期的に点検し、剥がれたら貼り直す
確かに、家中をガムテープだらけにするのは見た目が良くありません。
でも大丈夫、戦略的に使えば目立たずに効果を発揮できます。
効果を高めるコツは、貼り方と場所の選択。
ハクビシンの侵入しそうな小さな隙間や穴を中心に貼ります。
屋根と壁の接合部や、雨樋の周りなどが要注意ポイント。
粘着面を外側に向けて貼るのを忘れずに。
さらに、ハクビシンがよじ登りそうな場所には、幅10〜15センチほどのテープを貼ります。
これで、彼らの移動ルートを遮断できます。
「長期間の使用は大丈夫?」という疑問もあるでしょう。
確かに、屋外では劣化が早いので、定期的な点検と貼り替えが必要です。
でも、コストも手間も他の対策に比べればはるかに少ないんです。
ガムテープは、緊急時の応急処置としても使えます。
突然ハクビシンの侵入を発見したときも、とりあえずガムテープを貼って時間を稼げます。
身近で手軽、しかも即効性のある対策。
試してみる価値は十分にありますよ。
さあ、ガムテープでハクビシンの侵入ルートをシャットアウトしましょう!